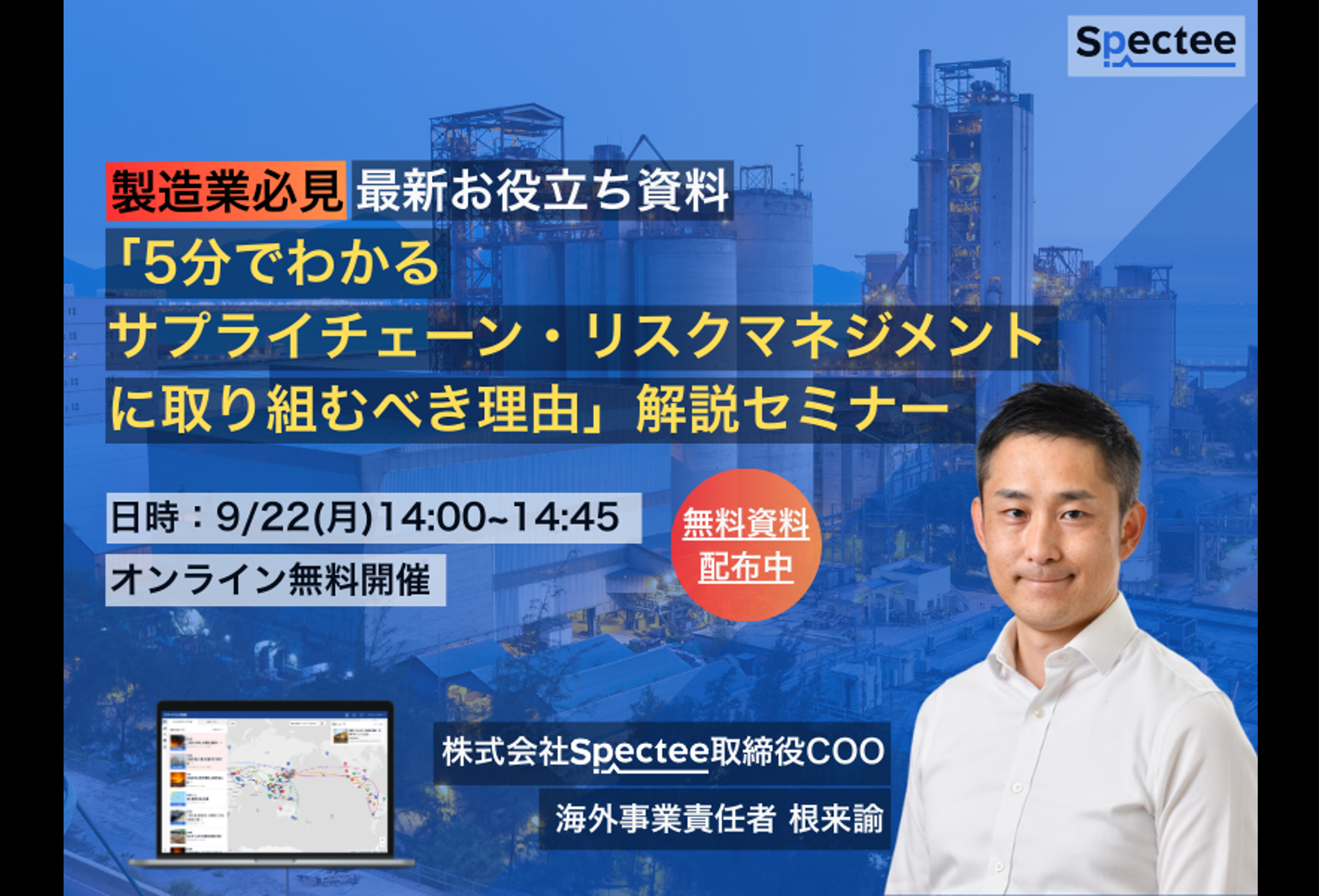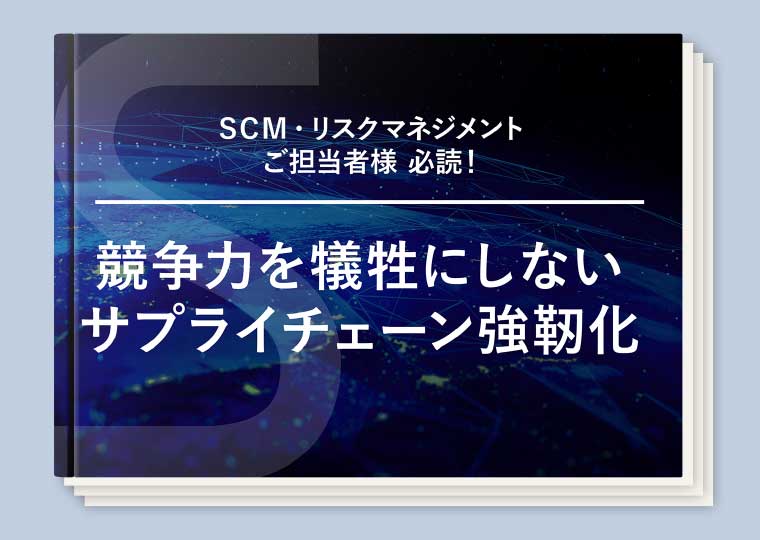【SFX’25】AIで危機に立ち向かう強靭なサプライチェーンへ ~サプライチェーンの未来とレジリエンスを考える~
- テクノロジー
- BCP・危機管理
- レジリエンス
- サプライチェーン
サプライチェーンの課題や未来を築くために必要なことを議論する「サプライチェーン・フューチャー・エクスペリエンス2025」(以下、SFX’25)が2025年3月14日にオンラインで開催されました。
本イベントでは、災害、パンデミック、地政学的なリスクなどを踏まえ、現時点での課題や、DXの促進、AIによる未来予測について議論が交わされました。有識者や経営者などのスピーカーが登壇し、今後のサプライチェーン強靭化やあるべき姿について、6つのパートに分かれてテーマに沿ったトークセッションを繰り広げました。
人口減少、労働力不足、2024年問題といった現状を分析しつつ、有事の際にも耐えうるサプライチェーンを構築するためのレジリエンス経営について、多角的な視点から意見が交換される有意義な一日となりました。
SESSION 1:
メガクライシスに備える! 経営戦略から考えるサプライチェーン・マネジメント 〜VUCAの時代に企業が生き残るためのレジリエンス経営とは?〜
SPEAKER
入山 章栄 氏(早稲田大学ビジネススクール 教授)
村上 建治郎(株式会社Spectee 代表取締役 CEO)
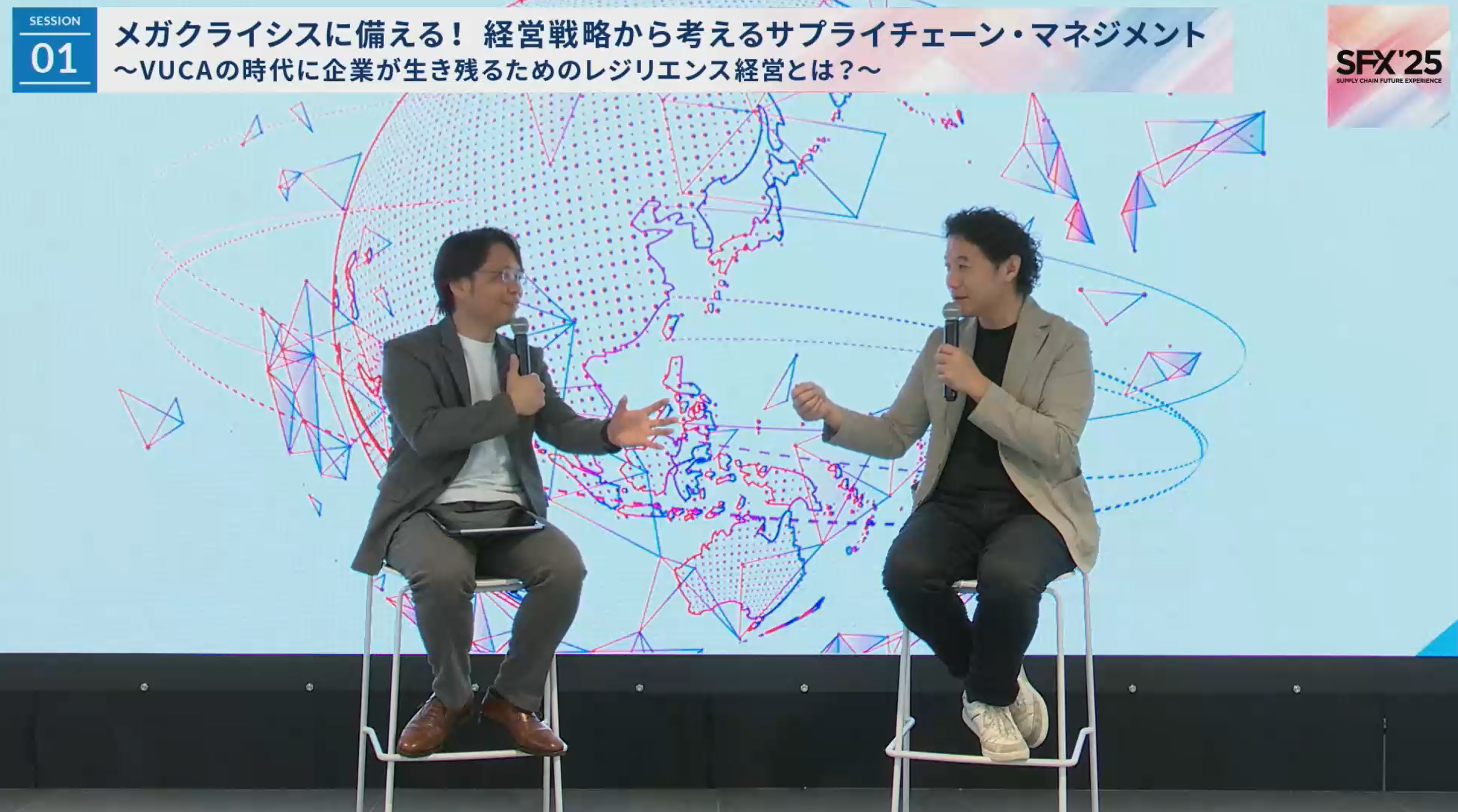
サプライチェーン強化が未来を切り拓く 企業を支えるレジリエンス経営とは?
イベントの幕開けとなるセッションでは、VUCAの時代に求められる企業のレジリエンス経営をテーマに議論が展開されました。
入山氏は、自動車メーカーのトヨタでの成功事例を挙げ、短期的な利益追求だけでなく中長期的な視点でのサプライチェーン強化の重要性を強調。特にトヨタが商品力を高め、サプライヤーと共に学び、安定した生産体制を築いている功績について語りました。
村上の「推進していくためには旗振り役も重要か」という質問に対し、入山氏は、コープさっぽろや、企業とドライバーをマッチングするCBcloud社のデジタル活用例を挙げながら、配送業のラストワンマイルの課題について触れ、AIやDXによる物流改革の可能性にも言及。人口減少が進む日本だからこそ、産業全体で取り組む抜本的なDXを進めやすい環境にあるはずと述べました。
最後に、入山氏は「日本はいわゆる第1のデジタル競争には負けたけど、これから本格化するデジタルとリアルが融合する第2のデジタル競争は、日本にとって大きなチャンス」と語り、製造や配送の現場の知見を生かし、ピンチをチャンスに変えるレジリエンス経営の重要性を強調しました。
SESSION 2:
データプラットフォームで実現する次世代サプライチェーン・マネジメント 〜AI・IoT時代における可視化と最適化〜
SPEAKER
久米村 隼人 氏(株式会社DATAFLUCT 代表取締役 CEO)
村上 建治郎(株式会社Spectee 代表取締役 CEO)
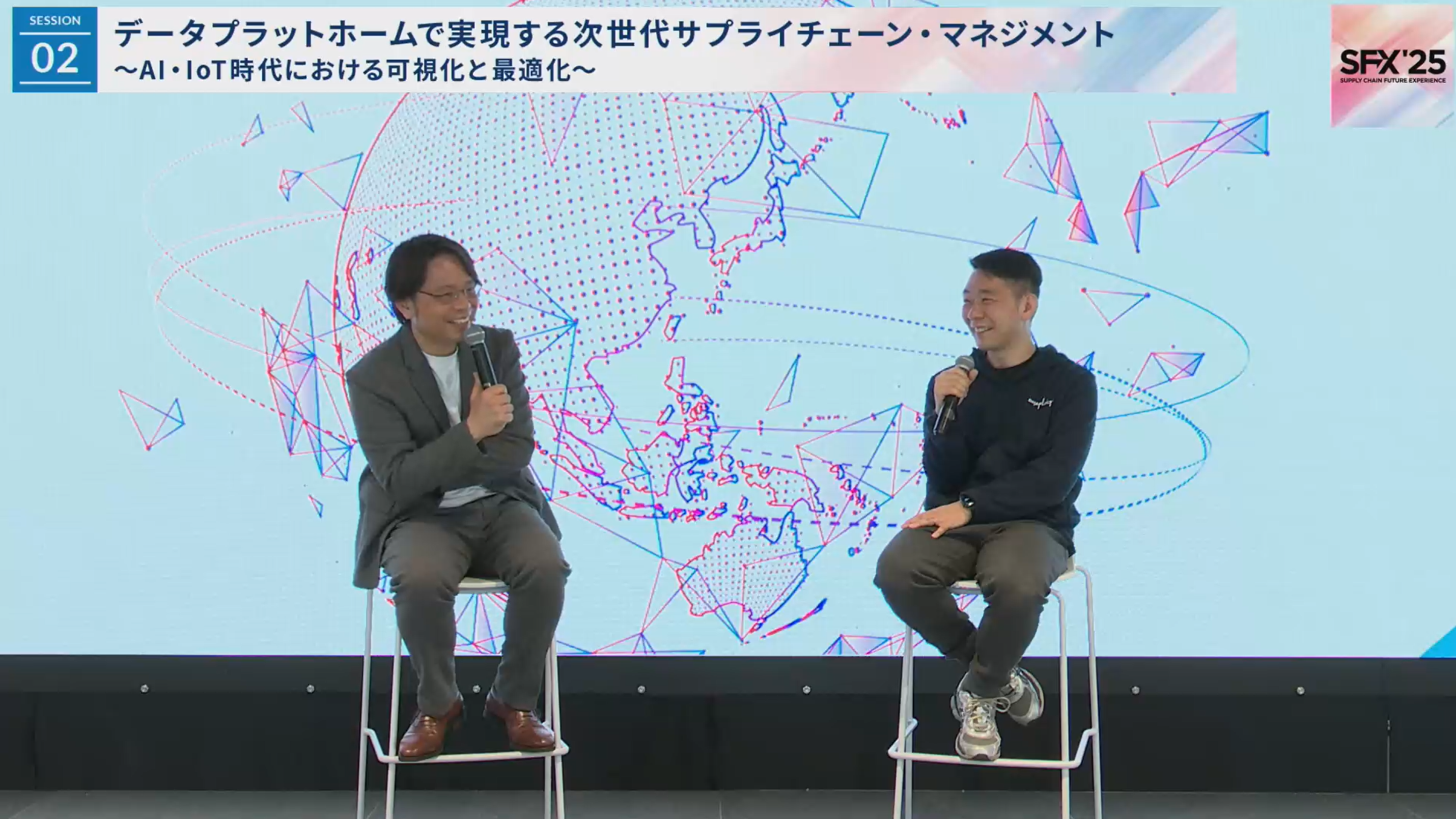
企業の眠れるデータを資産に変える戦略とは
本セッションでは、データ解析とAIを活用し、企業のサプライチェーン改革を支援するDATAFLUCTの取り組みについて掘り下げました。
久米村氏は、企業に眠るデータを活用すれば自動発注や需要予測が実現できる仕組みを紹介。特に、食品卸大手の国分グループでは、工場で毎日アルゴリズムを回してAIを活用し、全国のコンビニ向けの定番商品の自動発注・発送の効率化を進めている事例を挙げました。また、DX推進の課題として「データの9割は未整備である」と指摘。データの標準化とクリーニングの重要性を強調し、社内にデータサイエンティストがいない企業を中心に支援を行っていると振り返ります。
村上の「エンタープライズ企業にスタートアップが新規サービスを伝えていく壁をどう打ち破っているか」という質問に対して久米村氏は、新規取引先への営業アプローチについては、現場担当者との信頼構築を何よりも重視し、段階的に経営層へ提案を進めていくと語りました。
最後に、サプライチェーン領域のDXは参入障壁が高い一方で、AIとクラウドを活用すれば中小企業にも広く展開できる可能性があると強調。久米村氏は「企業に眠るデータは宝の山。それを生かすことで、日本の物流課題を解決していきたい」と意気込みを語りました。
SESSION 3:
物流革新が導く未来のサプライチェーン 〜デジタル時代の新たな潮流〜
SPEAKER
小野塚 征志 氏(ローランド・ベルガー パートナー)
根来 諭(株式会社Spectee 取締役 COO 海外事業責任者)
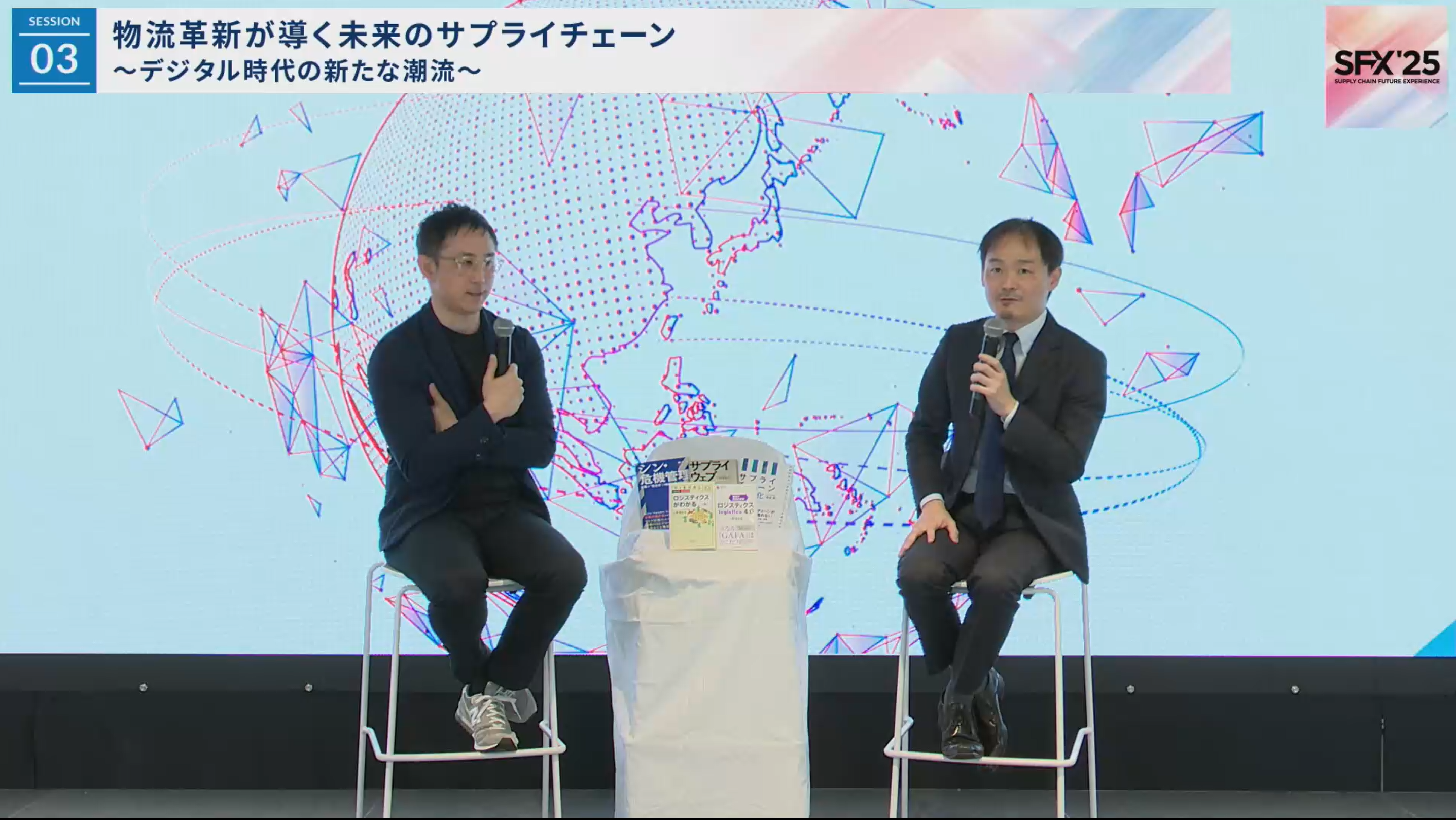
企業・業界・国を越えて改革が求められるサプライチェーンの未来予想図
『ロジスティックス4.0 物流の創造的革新』や『サプライウェブ 次世代の商流・物流プラットフォーム』の著者である小野塚氏と、『サプライチェーン強靭化―危機の時代に事業のレジリエンスを確立する』を執筆した根来が、物流革新の重要性と未来のサプライチェーンについて議論しました。
小野塚氏が、物流革新の進展とその影響を分析し、根来はサプライチェーンにおけるレジリエンスの重要性を訴えます。
2024年問題による物流の停滞懸念に対し、大きな混乱はなかったことに触れた一方、人手不足、DX推進の必要性は加速していると指摘。2025年4月から法律が変わり、荷待ち時間削減やCLO(チーフ・ロジスティック・オフィサー)配置が義務化され、物流が経営戦略に組み込まれることを踏まえ、自動運転トラックの導入が進み、間もなく稼働が始まるであろうと予測。
物流業界全体で標準化を図る「フィジカルインターネット」や、物の流通を企業や業界の垣根を越えた共通のインフラとして考える「サプライウェブ」についても触れられました。
デジタル化・標準化・自動化が進む中での課題としてAI活用や需要予測の精度向上はあるものの、経営戦略の一つとなる物流革新は、今後大きく推進することが期待できるでしょう。
SESSION 4:
AIが変えるグローバル・サプライチェーンの危機管理 〜「Spectee SCR」で実現するこれからのサプライチェーン・レジリエンス〜
SPEAKER
村上 建治郎(株式会社Spectee 代表取締役 CEO)
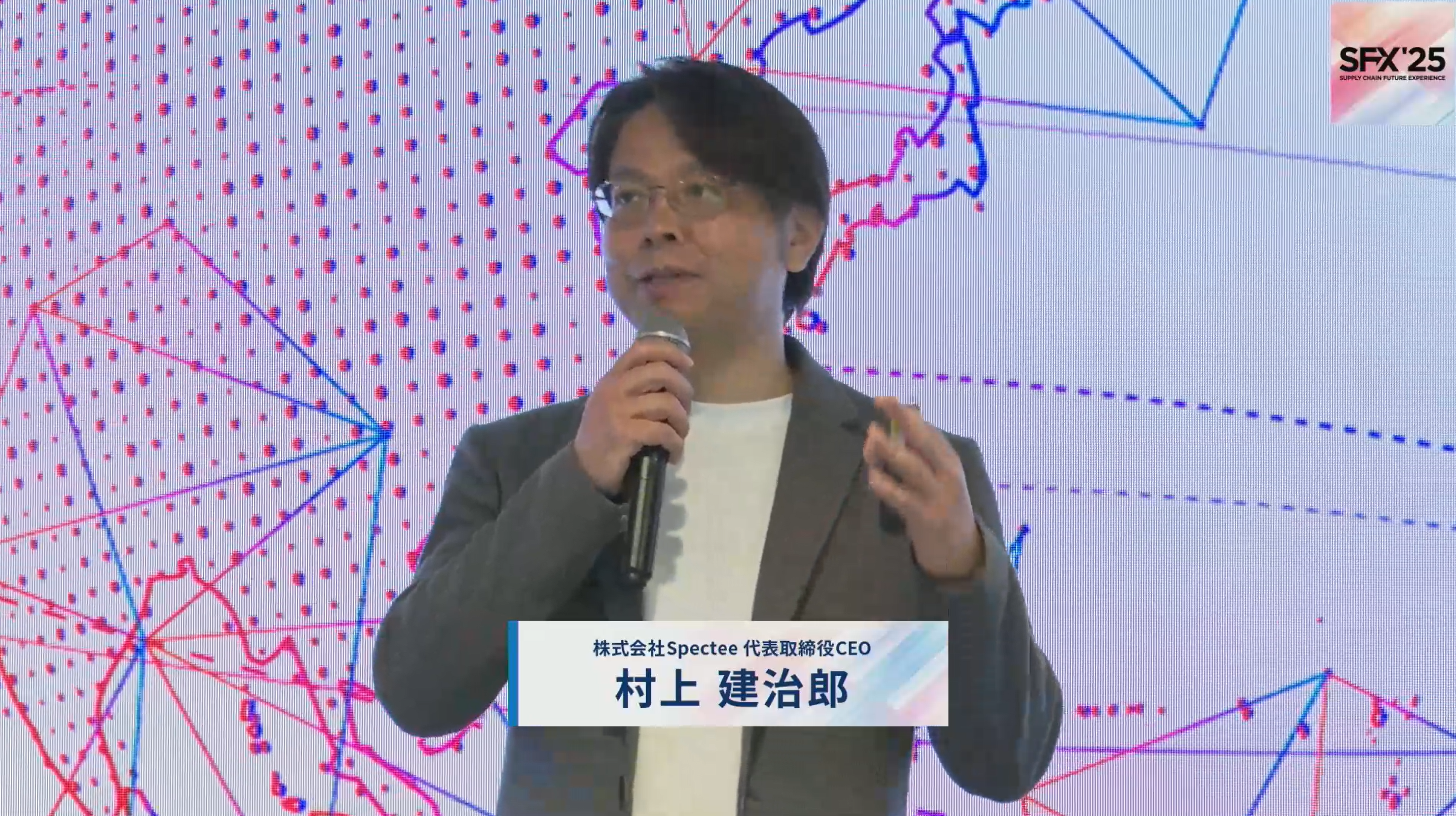
有事の際、サプライチェーンのボトルネックを解消する「Spectee SCR」
株式会社Specteeが提供する、AIを活用した危機管理ソリューション「Spectee SCR」と、サプライチェーン・レジリエンスの強化について語られました。
村上は、2011年の東日本大震災を契機に起業し、リアルタイムで危機を可視化するSpecteeを開発。SNS、人工衛星、交通データなど多様な情報源をAIで解析し、災害や事故の影響を即座に把握する仕組みであると紹介しました。
現在の世界の課題として、自然災害が急増中でその経済損失は3,800億ドル(58兆円)を超えること、グローバル・サプライチェーンが複雑化するほどにリスクや影響の幅は広がると同時に可視化が難しいことを挙げます。
その点、「Spectee SCR」なら、世界中のリスク情報をリアルタイムで可視化し、影響を受けるサプライヤーや納期遅延の可能性を即座かつ詳細に把握することが可能に。
村上は「24時間365日、あらゆるデータを解析し、危機への対応力を強化することで、企業のレジリエンス向上を支援していく」と述べ、今後もサプライチェーン領域での課題解決に取り組む姿勢を示しました。
SESSION 5:
製造業のサプライチェーン・レジリエンス 〜サプライヤーを巻き込んだBCPの取り組み〜
SPEAKER
木村 康弘 氏(ナブテスコ株式会社 BCP統括事務局 マネージャー)
根来 諭(株式会社Spectee 取締役 COO 海外事業責任者)
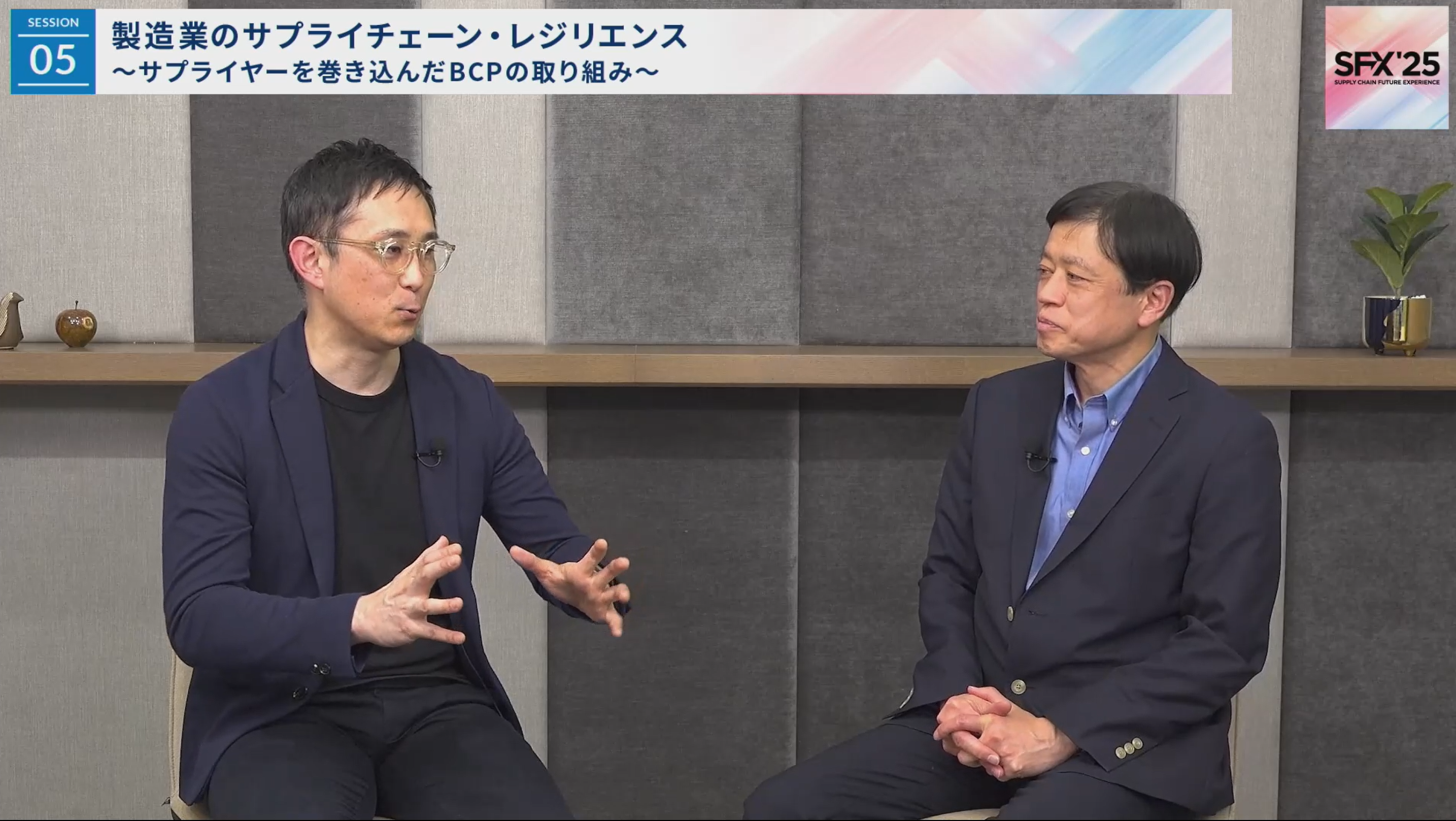
サプライヤーに伝播するBCPは、現場に寄り添いながらの実践と関係づくりが肝
本セッションでは、製造業におけるサプライチェーンのレジリエンスに焦点を当て、特にサプライヤーを巻き込んだBCP(事業継続計画)の重要性に焦点を当てて議論が行われました。
木村氏は、ものづくりの現場でBCPをどのように導入・機能させるのか、そしていかにして現場の自主的な取り組みを引き出し、レジリエンスを高めていくかについて語りました。現場における計画策定だけではなく、訓練や改善を重ねることの重要性、そしてサプライヤーへのBCP支援の実践についても触れています。
根来も、リスクが多様化する現代において、サプライチェーン全体でBCPを構築する必要性の高まりに共感を示し、特にサプライヤーの巻き込み方や、BCPを通じて企業全体のレジリエンスを高める方法について意見を交わしました。
また、木村氏はサプライヤーとの関係性や、BCPの教育・訓練の重要性についても説明し、BCPを実践に移すための具体的な方法論にも触れます。
最後に木村氏は、「分析や計画以上に大事なのは教育・訓練。現場に寄り添って問題点を自分ごとと捉えることが大事。意識を高める人材教育に注力し、歩幅を合わせて実践していく関係性づくりも大切」と締めくくりました。
SESSION 6:
新進気鋭スタートアップが語る、サプライチェーン強靭化への道
SPEAKER
佐藤 孝徳 氏(株式会社Shippio 代表取締役 CEO)
中原 久根人 氏(株式会社souco 代表取締役)
村上 建治郎(株式会社Spectee 代表取締役 CEO)
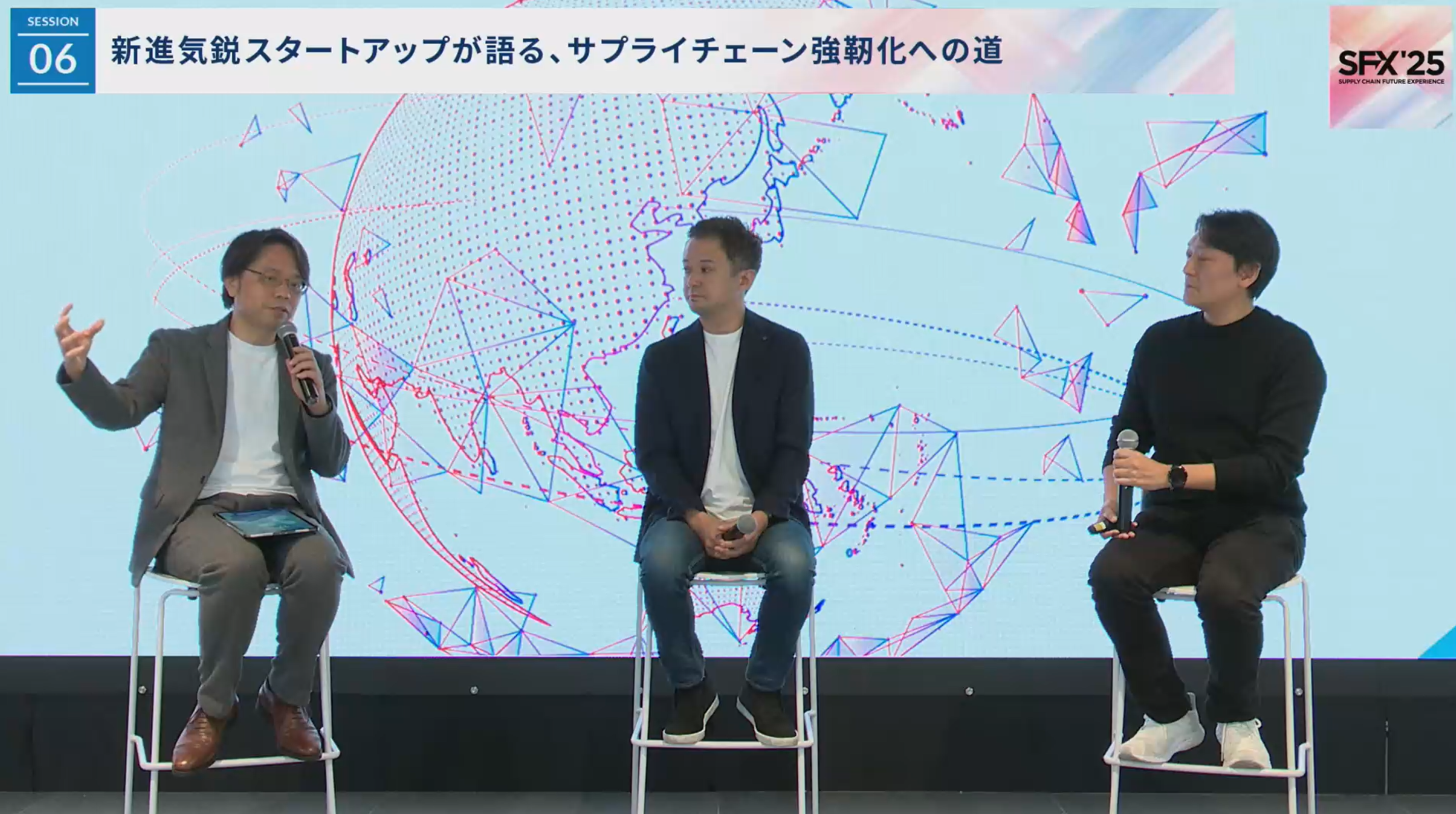
デジタル×プラットフォームで進化する物流の未来
最後は、サプライチェーンの効率化と強靭化に取り組むスタートアップ、株式会社Shippioと株式会社soucoの代表を迎え、それぞれの事業と業界革新への挑戦が議題となりました。
株式会社Shippioの佐藤氏は、国際物流のDXを推進し、1,400社以上の取引先に供給する同社の取り組みを紹介。起業のきっかけとして、三井物産株式会社での経験や自動車メーカーの物流部門との関わりを振り返り、物流領域の改革を志した経緯を語りました。
株式会社soucoの中原氏は、倉庫プラットフォームの潜在的なニーズに応え、3,000拠点以上のネットワークを構築したと起業の経緯を語りました。
村上が佐藤氏・中村氏にスタートアップでサプライチェーンや国際物流の領域に参入する壁について尋ねると、両氏は、商習慣が強く変化が起こりにくい物流業界におけるスタートアップならではの難しさを共有。一方で変化の一翼を担う視点から、佐藤氏はデジタル化がもたらす商習慣の変革の可能性を示し、中原氏はプラットフォーム事業特有の課題や既存事業者との調整を乗り越えてきた道のりとこれからについて語りました。
さらに佐藤氏は、スタートアップの参入の一つの方法として、複雑な通関業務に取り組むためにM&Aで解決したことを振り返ります。
村上は防災庁設置に向けた意見交換の場に出席した経験にも触れながら、政府を巻き込んで業界全体を変えていくタイミングではないかと投げかけると、両氏共に政府のサプライチェーン強靭化政策に賛同。
最後は、一同が政府のデジタル化推進に期待を寄せるとともに各社の技術を活用することで日本の物流の強靭化に寄与していきたいと決意を語りました。
VUCA時代をしなやかに乗り越える
未来へ繋ぐサプライチェーン・レジリエンス
かつて効率化やコストダウンを追求してきたサプライチェーン・マネジメントは、2024年問題や近年の法改正を受け、また災害時にも対応できる強靭性(レジリエンス)が求められています。
今回の「未来をつくるサプライチェーン・レジリエンス SFX’25」では、そのような背景を踏まえ、有識者や経営者など多様な視点から現状分析と未来への提言が行われました。具体的には、AI・DXなどを含めた技術革新、パンデミックや地政学的リスクなどの予測不可能な事態に備えるBCP、そして企業や業界の垣根を越えた協力の不可欠性が語られました。人口減少や労働力不足が深刻化する現代において、多くの革新的なアイデアが実現に向けて動き始めていることが感じられる時間となりました。
VUCAの時代において、サプライチェーン強靭化の実現への挑戦はすでに始まっています。本イベントでの熱い議論が、未来の変革へと繋がることを期待せずにはいられません。