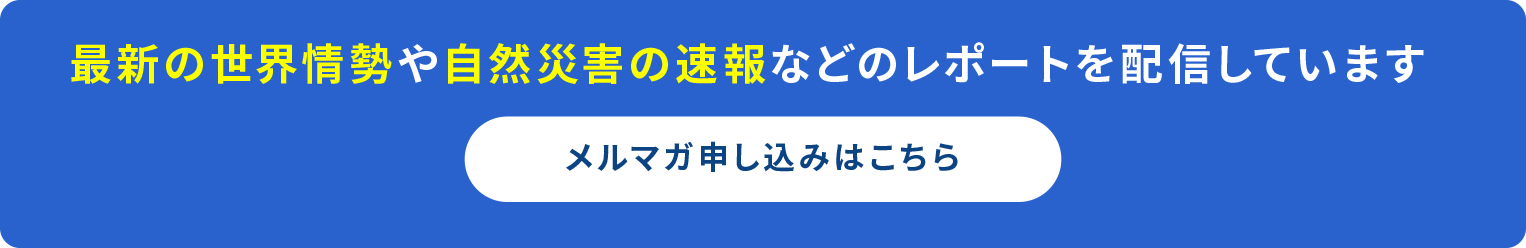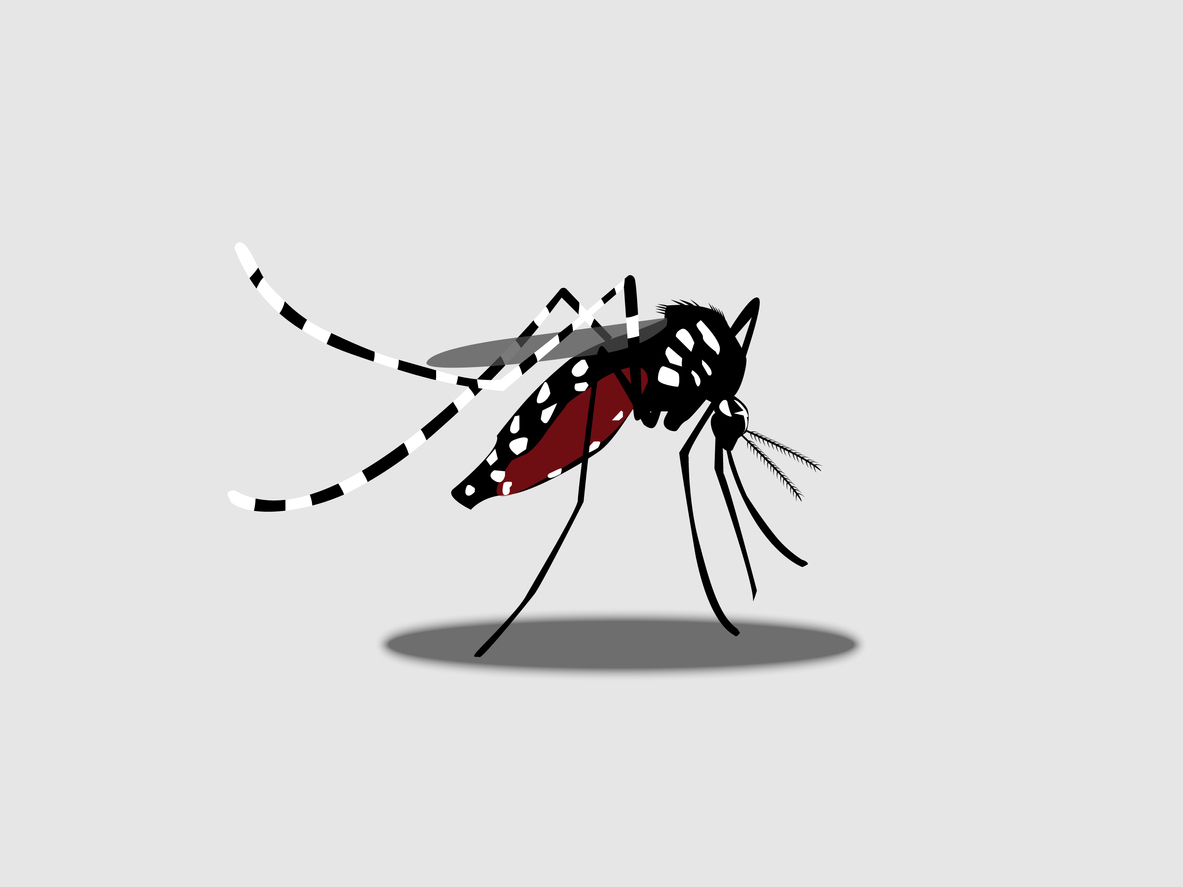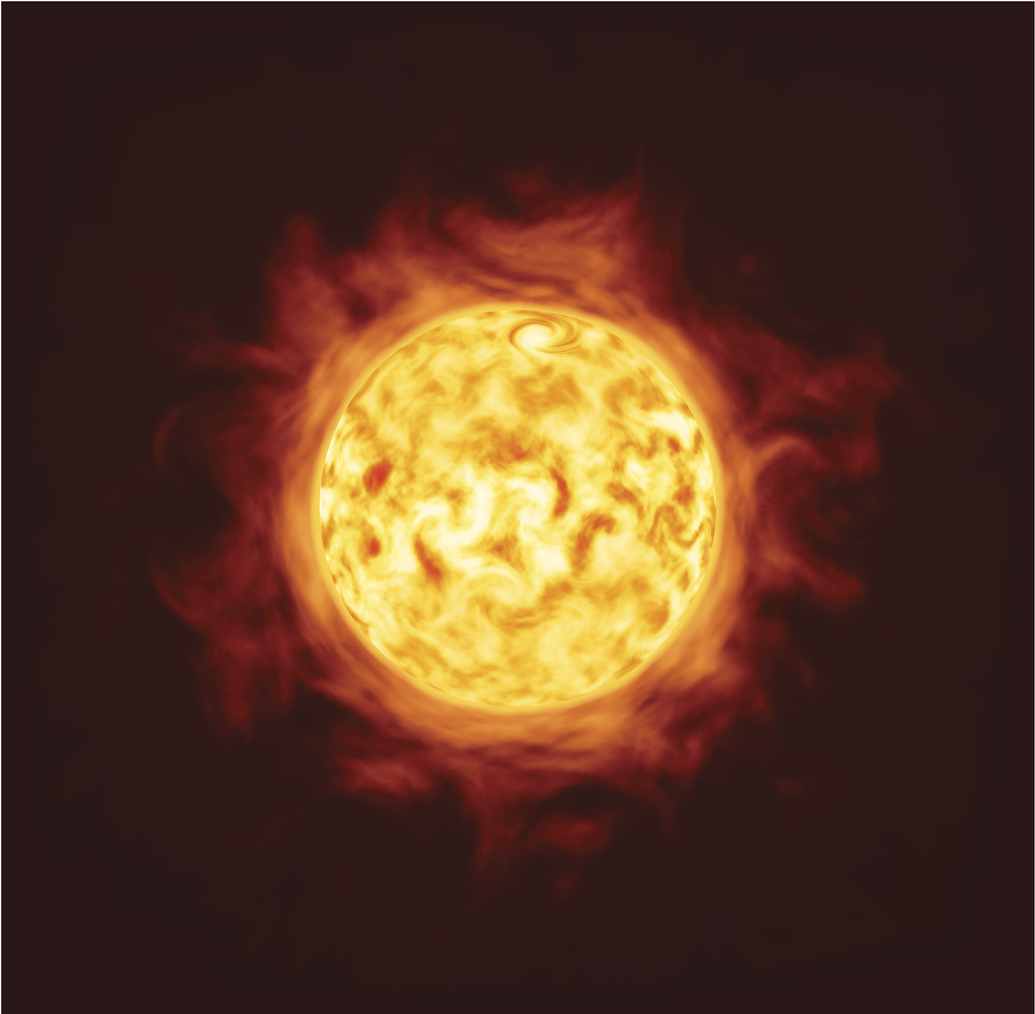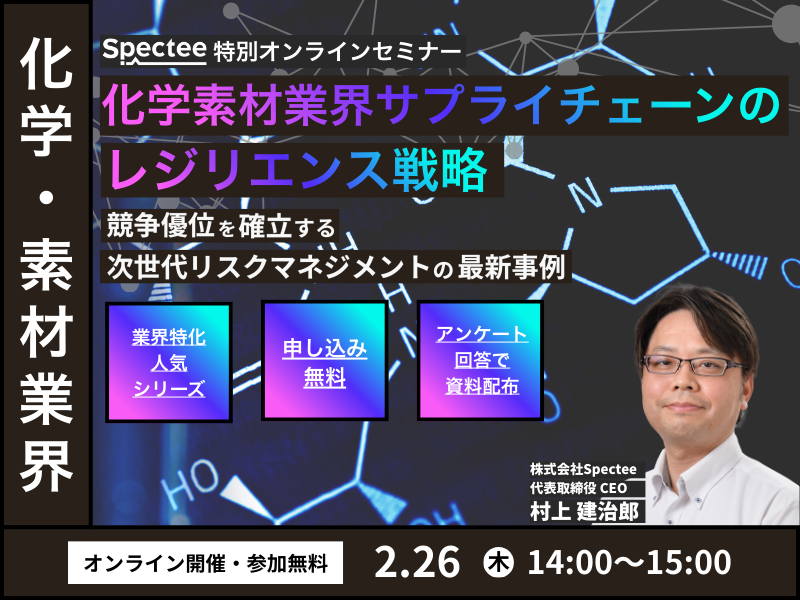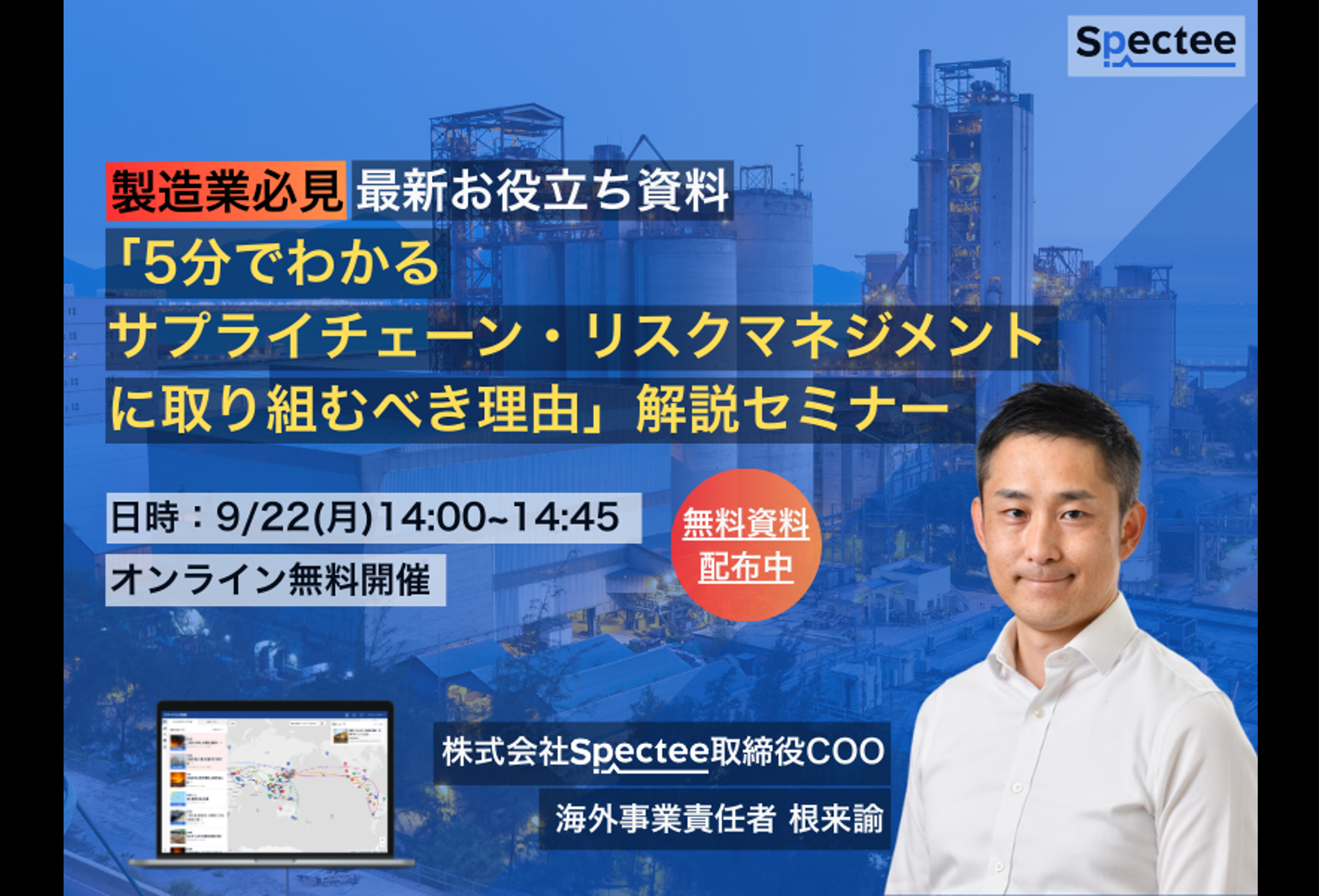我々は偽情報とどう向き合うべきか SNS分析の現場から考える(下)
- 防災
- BCP・危機管理
- ビッグデータ
- レジリエンス
前回に続き、今回も、ブラジル・リオデジャネイロで開催された「Global Fact 12」での議論に加え、業務における筆者自身の経験を踏まえながら、SNS上の偽情報対策などについて考えてみたいと思います。
SNS時代の偽情報対策:情報の保存とコラボの最前線
今回の「Global Fact12」では、偽情報対策に関するさまざまな技術が紹介されました。その中でも筆者の目を特に引いたのは、「情報の保存」や「ウェブサイトのアーカイブ」に関する技術です。 たとえば、著名人の発言をファクトチェックする際には、過去と現在の発言を比較する必要が頻繁に生じます。しかし過去の発言が削除されてしまうことも多く、その場合でも「証拠」を残せる仕組みが欠かせないといえます。 実際、近年メディアのファクトチェックに力を入れている仏AFP通信メディアラボのDenis Teyssou氏と、ウェブ保存で知られる米非営利団体「ウェイバックマシン」のMark Graham氏らが協力し、SNS上の偽情報の保存に関するワークショップを開催していました。従来は難しかった一部のSNS情報の保存を可能にするこうした試みは、大きな関心を集めていました。
このように異なる組織同士が「コラボレーション」し、新しい取り組みを形にしている点も、今回のGlobal Fact12の大きな特徴といえます。その象徴が、偽情報対策に特化したチャットボット「Global Fact-Check Chatbot」を開発したことでしょう。 このツールは、世界のファクトチェック団体で構成される「International Fact-Checking Network(IFCN)」の加盟組織から提供された記事や、報道を収録したデータベースを活用し、58カ国から毎日届くデータを更新することで、選挙、感染症の危機、地域紛争や戦争といった局面に対応できるよう設計されているといいます。世界中の団体が力を合わせてこうした実用的なツールを生み出している姿には、筆者も羨望の念を抱かずにはいられませんでした。
日本におけるファクトチェック連携の課題と可能性
ここで翻って、日本の状況に目を向けてみたいと思います。前回のレポートでも触れましたが、能登半島地震の際、筆者は自らの業務の中で、単独で情報の真偽を見極めることに限界を感じたことを記しました。これに関連して、武蔵大学の奥村信幸教授は、世界ではメディア間の「コラボレーション」が進む一方で、日本ではその動きが遅れていると指摘しています。また、情報の真偽はメディア間で共有可能であり、特に災害で大きな効果を発揮するとの見解も示されています。 筆者もこの意見におおむね同意します。より正確に述べるなら、必要なのはメディア同士にとどまらない諸団体との「ゆるやかな連携」だと考えています。たとえば、筆者の業務では、河川管理者や高速道路会社の担当者が、SNSに投稿された画像のごく一部から、瞬時に場所を特定する姿を目の当たりにしてきました。現場の知識を持つ彼らの存在は、メディアや民間団体だけでは補えない強みとなり得るでしょう。

他方で、国内ではファクトチェック団体に政府資金を投入すべきかどうかが議論になっています。特に、ファクトチェック団体関係者の声として「政治や行政、警察などとの関係には慎重すぎるほど慎重でなければなりません」との声も出ており、報道実務経験のある筆者としても、この懸念はよく理解できるものです。 ただし、災害や危機の現場を考えれば、行政が加わることで情報の信頼度が高まる場面もあるのではないでしょうか。たとえば台風で河川が氾濫したというSNS情報を検証する場合、マス・メディアや民間団体に加えて、河川を管理する行政が関われば、より正確な検証が可能になると考えます。 筆者は国内外のファクトチェック団体、偽情報対策やOSINTの勉強会等に積極的に参加し、関係者と議論を重ねていますが、それは外部の諸団体との人的ネットワークをつくり、これらのゆるやかなネットワークが、将来的には必ず業務に資すると確信しているからです。
偽情報に立ち向かう国際的ネットワーク設立へ
今回のGlobal Fact12には、日本から筆者のほか、香港でファクトチェック団体「ANNIE」を運営する鍛治本正人香港大学教授、日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長、リテラシー教育に取り組むインフォハント代表の安藤未希代表が参加していました。 現在、鍛治本教授を中心に、アジア太平洋地域のファクトチェック団体でゆるやかな連合体をつくる構想が進められています。実現すれば、各国が抱える課題やノウハウを共有でき、偽情報への対応力を地域全体で底上げすることが可能になります。特に日本の自然災害対応や危機管理の経験が国際的に共有されれば、相互に学び合う循環も期待できます。スペクティ・アンカーチームとしても、こうした動きに積極的に参加していきたいと考えています。
(大久保 陽一)
October 29, 2025
信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!
スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。
また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/
- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)