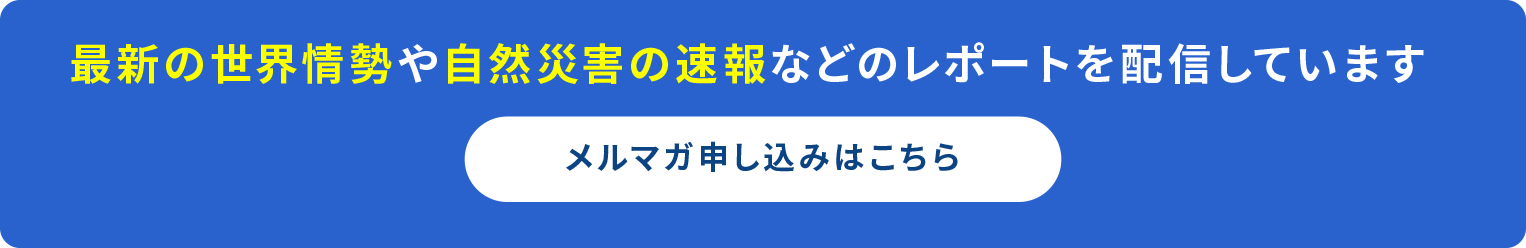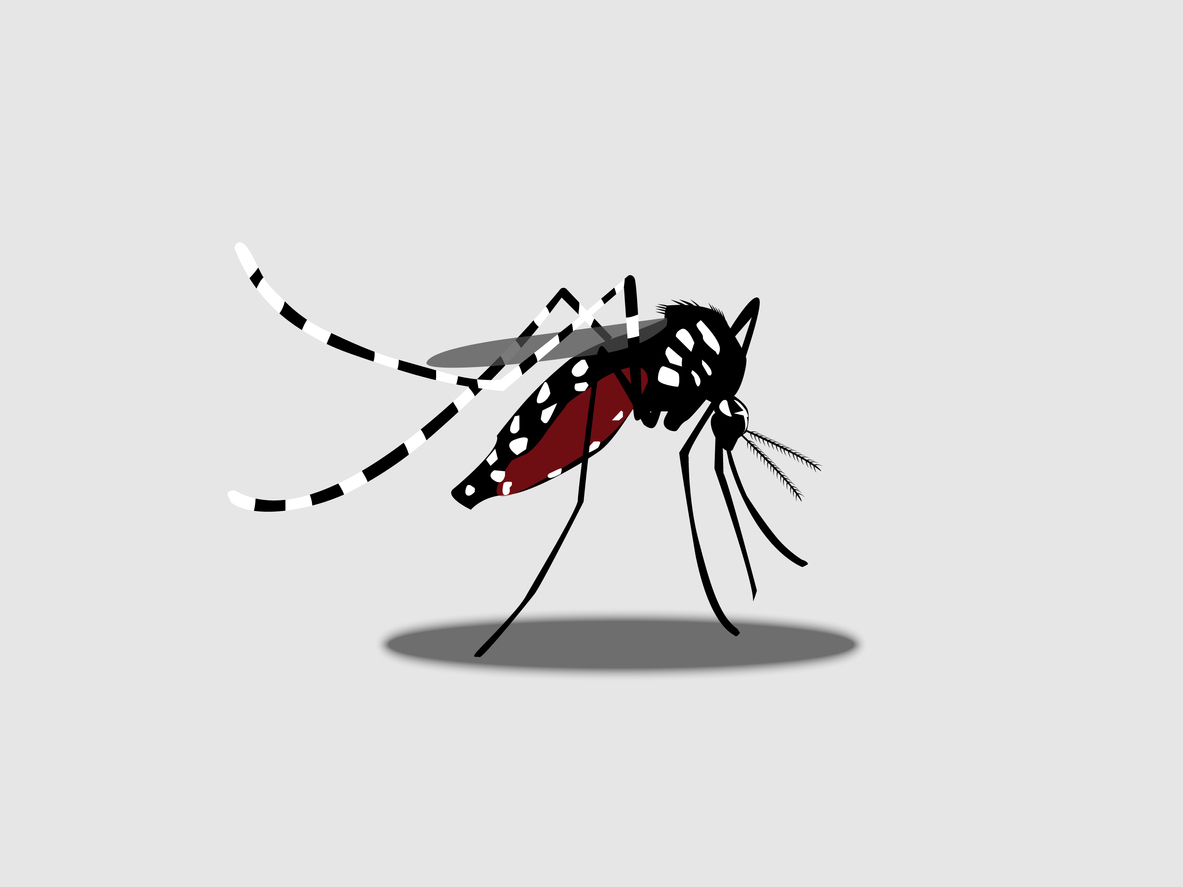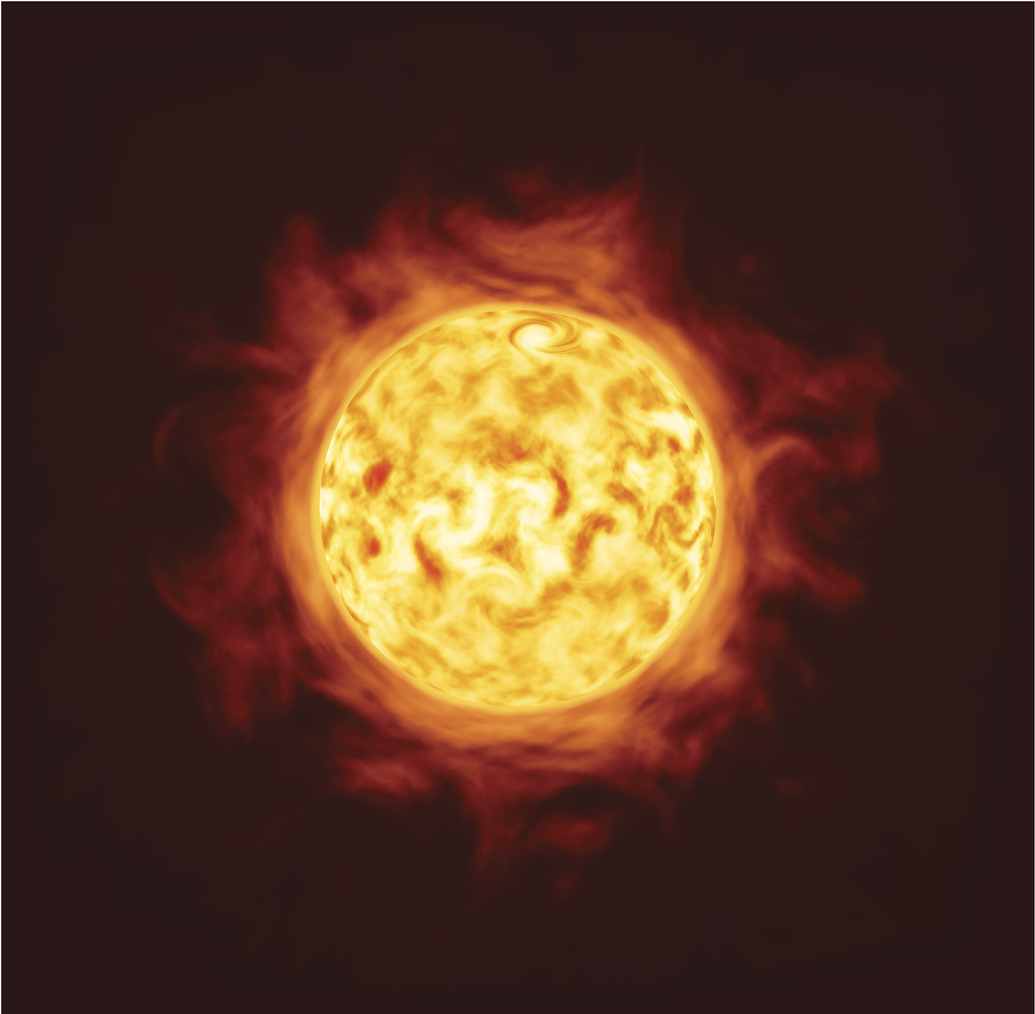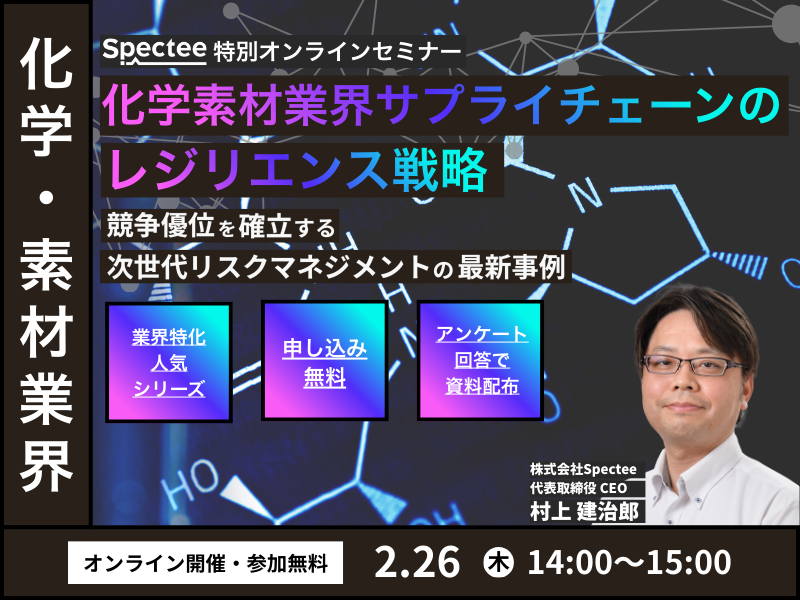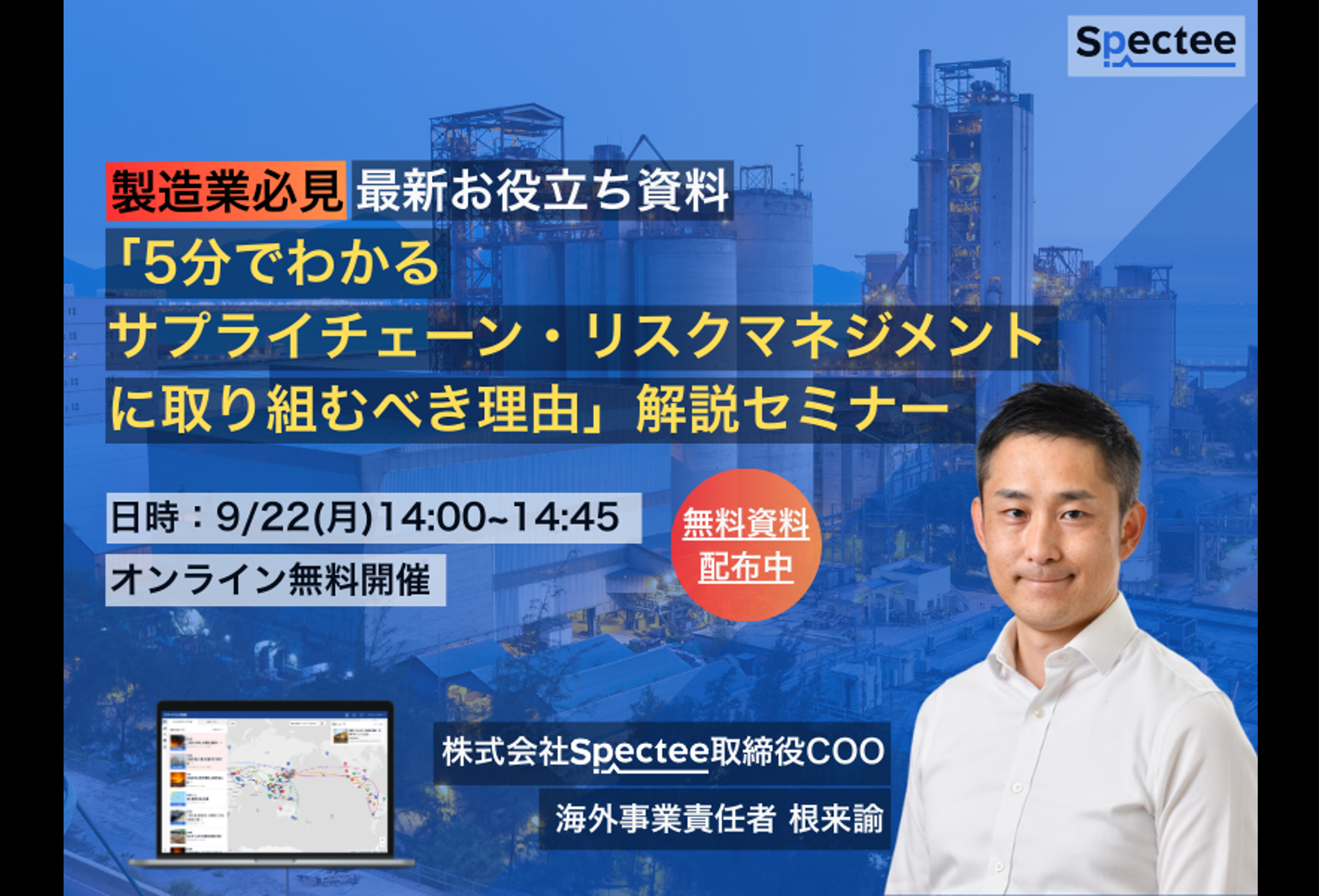【日刊工業新聞連載:第一回】「企業経営における「レジリエンス」とは
- 気候変動・気候危機
- 防災
- テクノロジー
- BCP・危機管理
- ビッグデータ
- レジリエンス
- サプライチェーン
- 自然災害

2025年4月より、Specteeは日刊工業新聞で「レジリエンス経営の未来」と題した全24回の連載を開始しました。「災害に強い企業を目指したい」「テクノロジーを活用した危機管理に関心がある」など、レジリエンス経営にご関心のある方は、ぜひ本レポートをご覧ください。連載で掲載された記事を順次転載してまいります。
自然災害の多発や政治的な混乱、急速なAI技術の発展など、我々は不確実性に満ちた時代に生きている。企業はどのように困難を乗り越え、さらなる発展を図っていけばよいのだろうか。本連載では、防災・危機管理ソリューションを提供する株式会社Specteeのメンバーで、24回にわたって「レジリエンスと経営の未来」というテーマで解説をしていきたい。初回は最近注目が集まっている「レジリエンス」という言葉について、企業経営の文脈から定義づけてみたい。
「レジリエンス」の意味
「レジリエンス(resilience)」という言葉は元来、物質が外からの衝撃や力を受けて変形し、元の形に戻ろうとする性質を表す物理学の用語である。そのため、「回復力」「復元力」「弾力」などの訳語が充てられることが多い。転じて、心理学の世界においては、困難や逆境、ストレスなどに直面した際に、それを乗り越えて回復する能力を指す。 具体的にレジリエンスという言葉の持つ意味をイメージするには、似た意味を持つ「ロバストネス(Robustness)」という言葉(「堅牢性」「頑健性」などと訳される)と対比するのが良いかもしれない。有名なイソップ寓話「樫と葦」において、樫の木は頑強で力強く、ロバストな存在と言える。普通の風に吹かれたくらいではビクともしないが、あまりに激しい暴風に見舞われた際にはへし折れてしまい、二度と元の状態には戻らない。その一方で、葦は弱い風に吹かれただけで曲がってしまうものの、暴風に見舞われたとしてもそれを受け流し、また元の状態に戻っていくしなやかさを備えている。このケースにおいて、葦は樫の木と比べて「レジリエント」な存在と言えるだろう。

企業経営にレジリエンスが求められる背景
このレジリエンスという性質が企業経営において注目を浴びているのはなぜだろうか。その背景には、急速な変化と不確実性が増大している現代の経営環境がある。気候変動や地政学リスクの高まり、パンデミックの脅威、これまでにない技術革新の加速など、多岐にわたる要因が企業を取り巻く環境を大きく変化させている。このような状況下では、予測不可能な危機や変化に直面することが避けられず、それを乗り越えていく能力が求められるのである。
第一に、リスクの多様化と危機事象発生頻度の増加が挙げられる。2024年は世界で記録的な暑さとなり、地球の平均気温の上昇を産業革命以前と比べて1.5℃以内に抑えるという、パリ協定で設定された国際的な目標を既に上回ってしまった。この気候変動による自然災害の増加は、世界中で発生している水害や異常な気温、また山火事や干ばつなどの頻発という形で我々の目の前に現実的な脅威として立ちはだかっている。日本に関して言えば、南海トラフ地震や首都直下地震など甚大な損害をもたらす地震の発生確率が上がっており、300年以上に渡って噴火していない富士山についても警戒が必要であるなど、災害大国として様々なリスクに直面している。さらには地政学リスクの高まりも特筆すべきものがある。第二次世界大戦以後、世界はグローバル化を深化させてきており、自由民主的な価値観が優勢になるという楽観的な見方もあったが、現実には権威主義的な国が経済成長と共に台頭する中で、パワーバランスが大きく崩れてきている。ロシアのウクライナ侵攻やパレスチナを巡る紛争は、その一端が戦争という形で表出したものと言うことができる。米国のトランプ大統領が就任して早速ドラスティックな政策を次々打ち出しているが、それが様々に影響を及ぼし、今後国際情勢は先の予測できない状況が続いていくだろう。さらに、また新型コロナウイルス感染症の爆発的流行のようなパンデミックがいつ起こるかもわからない。これら、今まで想定していなかった、または想定を超えたリスクが、事業を継続することを妨げたり、サプライチェーンを途絶させたりしていることを受けて、企業は危機に対処する能力を備えなければならない。
第二に、競争環境の変化もレジリエンスが求められる要因である。近年は技術革新のスピードが異常に早く、従来のビジネスモデルが陳腐化するスピードが加速している。このような状況では、変化に適応し続ける能力が企業の持続可能性を左右する。特に人工知能(AI)技術については、生成AIの急速な進化によって、これまで人間の聖域だと思われた「創造」という領域がテクノロジーによって担われるようになってきており、これまでとは桁違いの規模とスピードでゲームチェンジが起きていくものと思われる。そうした中で自社の事業を守り発展させていくためには、変化に飲み込まれることなく、適応して自らを進化させるレジリエンスを身につける必要がある。
第三に、企業に対するステークホルダーからの期待の変化も無視できない要因である。かつての企業の目的な利益の追求・最大化であって、株主価値の向上が最優先とされました。しかし今の消費者、従業員、投資家、地域社会など、企業が関わるステークホルダーはそれに加えて、持続可能性や社会的責任、環境への配慮、透明性といった要素を重視する傾向を強めている。これに応えるためには、危機的な状況でも価値を提供し続ける能力が必要である。例えば、サプライチェーンの問題が発生した際にも迅速に復旧し、顧客に安定したサービスを提供する企業は、社会的責任を十全に担う存在として、その価値が高く評価されるだろう。
企業がレジリエンスを高めるには
それでは、企業がレジリエンスを高めるためにはどのようなことが必要でしょうか。米国プリンストン大学教授のマーカス・K・ブルネルマイヤー氏は、その著作「レジリエントな社会 危機から立ち直る力」の中で以下をレジリエンスの要素として挙げています。
①順応性・柔軟性・変化能力(状況の変化に適応する能力)
②代替可能性(特定の資源や手段に依存しないこと)
③多様性と開かれた心(多様な視点とアプローチを持ち、包括的な考え方をすること)
④バッファと冗長性(予期しない事態に備えて余裕や予備を確保すること)
⑤リスクへの暴露(小さなショックを経験して対処法を学び、備えること)
ここに挙げられた5つの項目全てが大切ではありますが、最もレジリエンスの本質を表しているのが1番目に挙げられた「順応性・柔軟性・変化能力」ではないでしょうか。我々の社会や環境は常に変化を続け、同じ状態に留まることはありません。そうした絶え間ない変化に対して自らのあり方を変えていくこと。そして新しい状況に対して適応していくこと。これこそがレジリエンスであり、いつどのような危機に見舞われるかわからない不確実性が極めて高い時代において、企業が生き抜いていくのに最も大切な要素なのではないでしょうか。
企業がレジリエンスを身につけるためには、柔軟性と適応力を高め、予測不可能な状況に効果的に対応できる体制を構築する必要があります。そのために、具体的には以下のようなアクションが必要になると考えられます。
リスクマネジメント活動
企業は、自らを取り巻く様々なリスクを特定・評価して対策を講じることが求められます。そのためには自社にリスクマネジメント機能を備える必要があります。危機に見舞われた際に事業の継続を目指すBCP(事業継続計画)や組織体に発生するあらゆるリスクを統合的に把握・評価・最適化するERM(全社的リスクマネジメント)など、手法やフレームワークは様々ありますが、「想定外」の事態を無くし、危機に対応するための準備をすることが大切です。
柔軟な組織文化の醸成
レジリエンスを身につけるためには、柔軟で適応力のある組織文化が不可欠です。従業員が変化に対して柔軟に対応できるよう、変革を恐れずに受け入れる文化を育てることも重要になります。また、従業員の意見を尊重し、迅速な意思決定を可能にするコミュニケーション体制を構築することも、危機の発生時に組織の強みになるでしょう。テクノロジーを活用すること、そしてイノベーションを起こすこと。変化に抵抗するのではなく、変化をチャンスと捉える姿勢を持つことは、企業が競争力を維持して生き抜いて行くのに大きな武器となります。
サプライチェーンの強靭化
様々な危機にさらされるサプライチェーンの脆弱性を減ずるために、自社のサプライチェーンを強靭化することが必要です。サプライチェーンを可視化してどこに危機が潜むのかを評価・分析し、その上で冗長化やサプライチェーンの組み替え、サプライヤー・マネジメントの強化などによって「お客様が必要な時に必要なモノを必要な量届け」続けられる体制を作り上げることは、企業価値の向上につながるものです。
レジリエンスを高めることは、単に危機的な事象に対して企業が強くなるだけではなく、将来的な成長のための基盤を強化するものだ。今の不確実性の高い時代において、「絶え間ない変化に対する適応能力」を企業の基盤や戦略に埋め込むことは、経営にとって最重要事項と言っても過言ではないのではないだろうか。本連載を通じて、「レジリエンス経営」とは何かを読者の皆様と一緒に考えていければ幸いである。
(根来 諭 Spectee取締役COO 海外事業責任者)
紙面掲載日 April 09, 2025
信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!
スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。
また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/
- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)