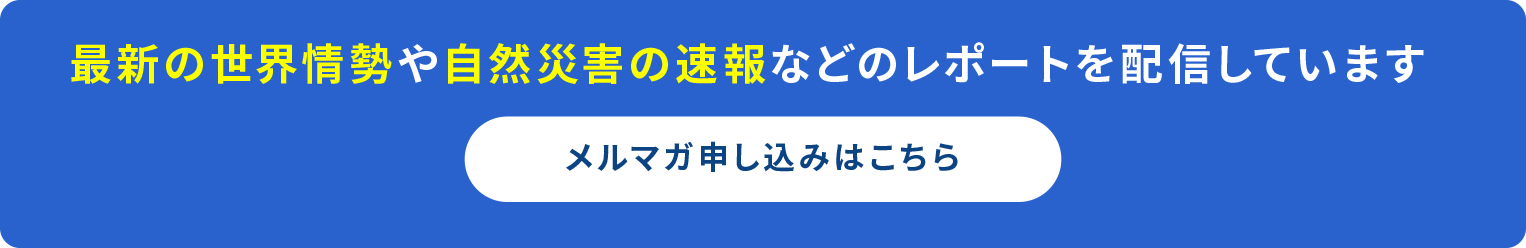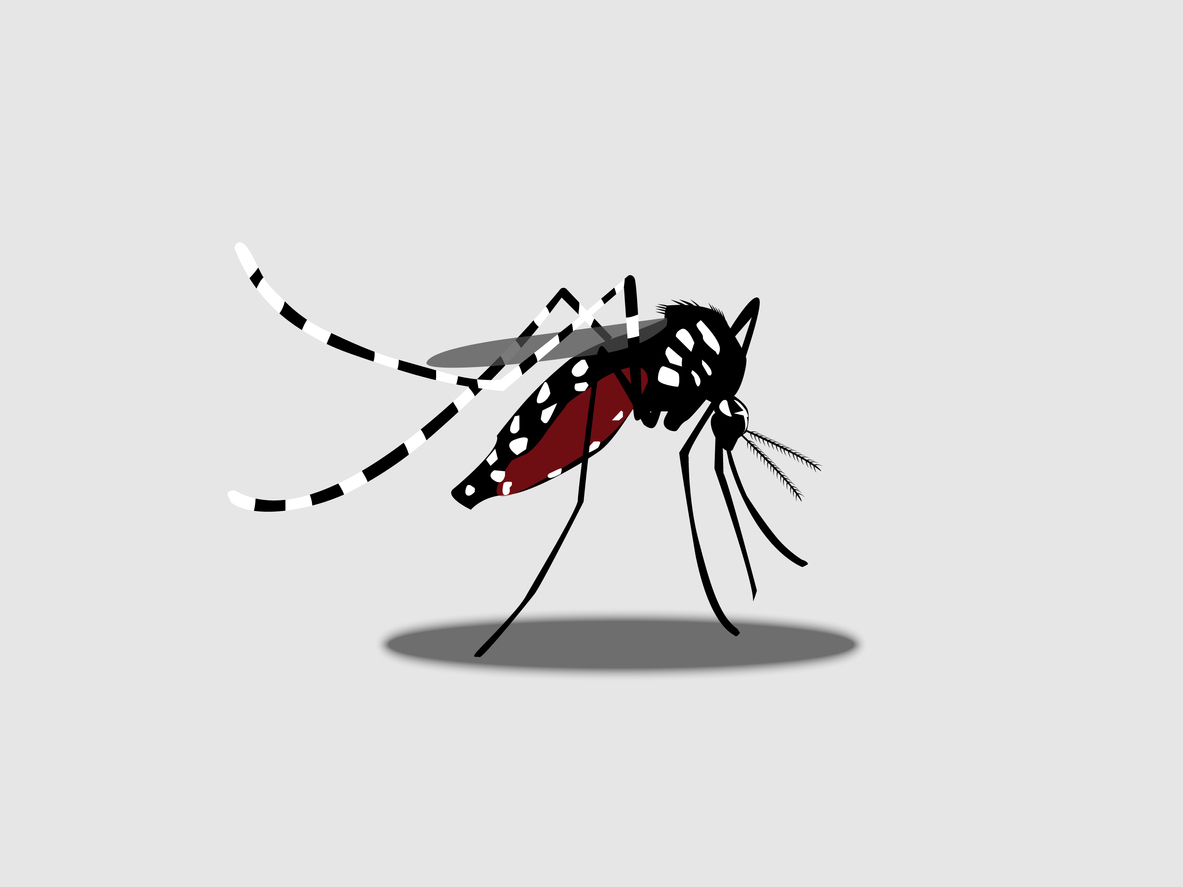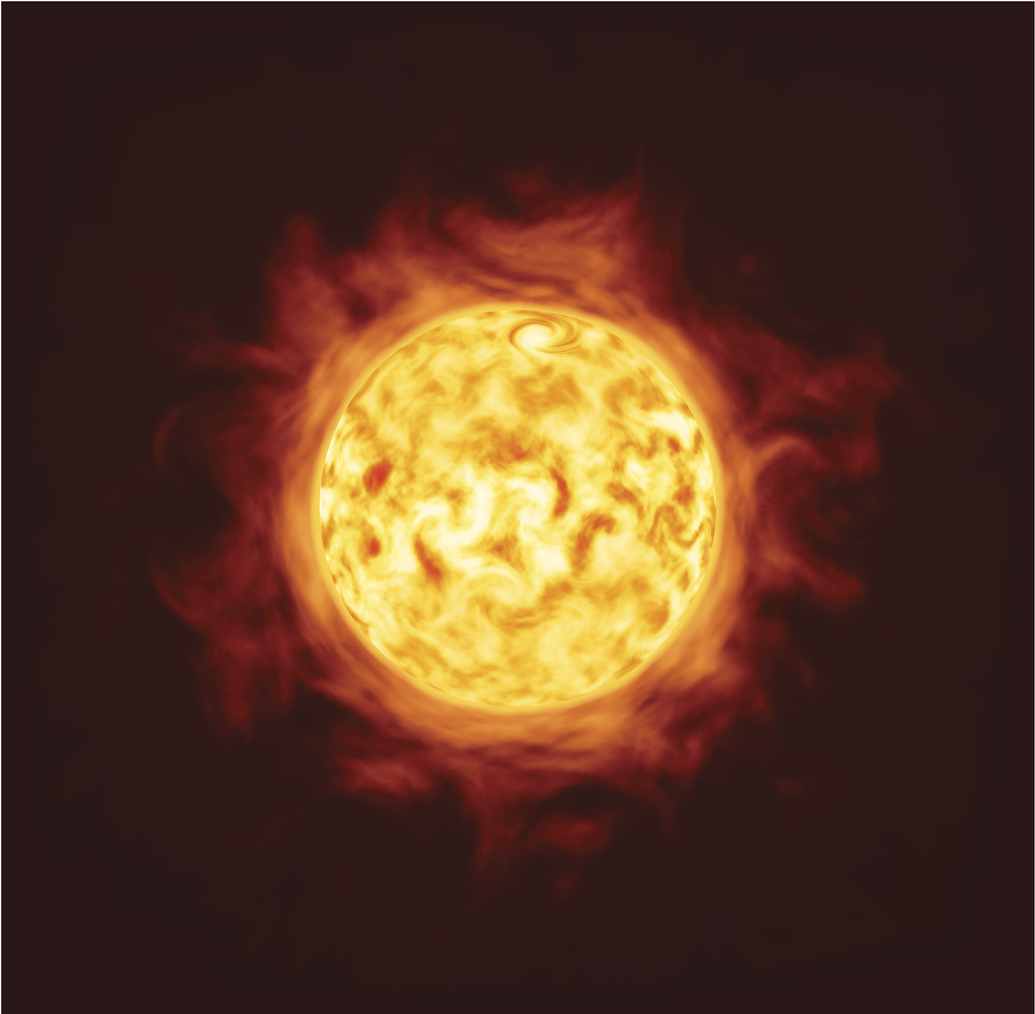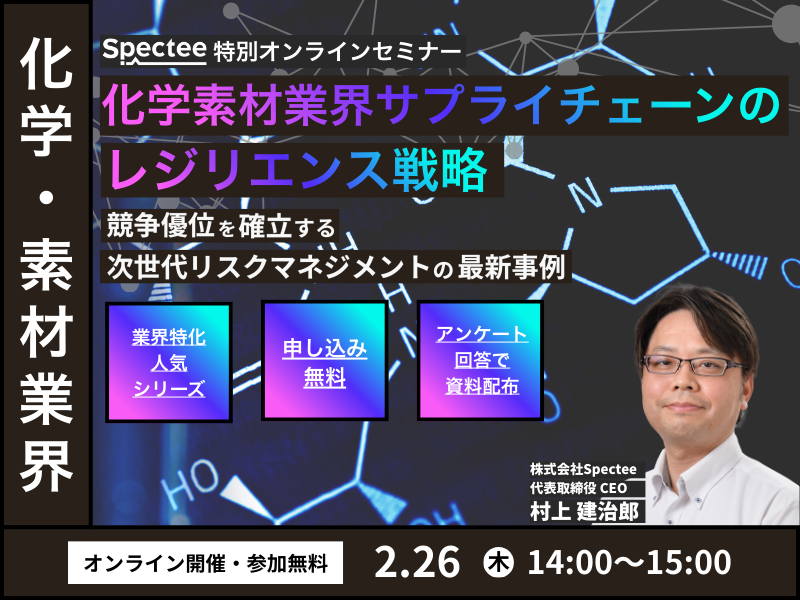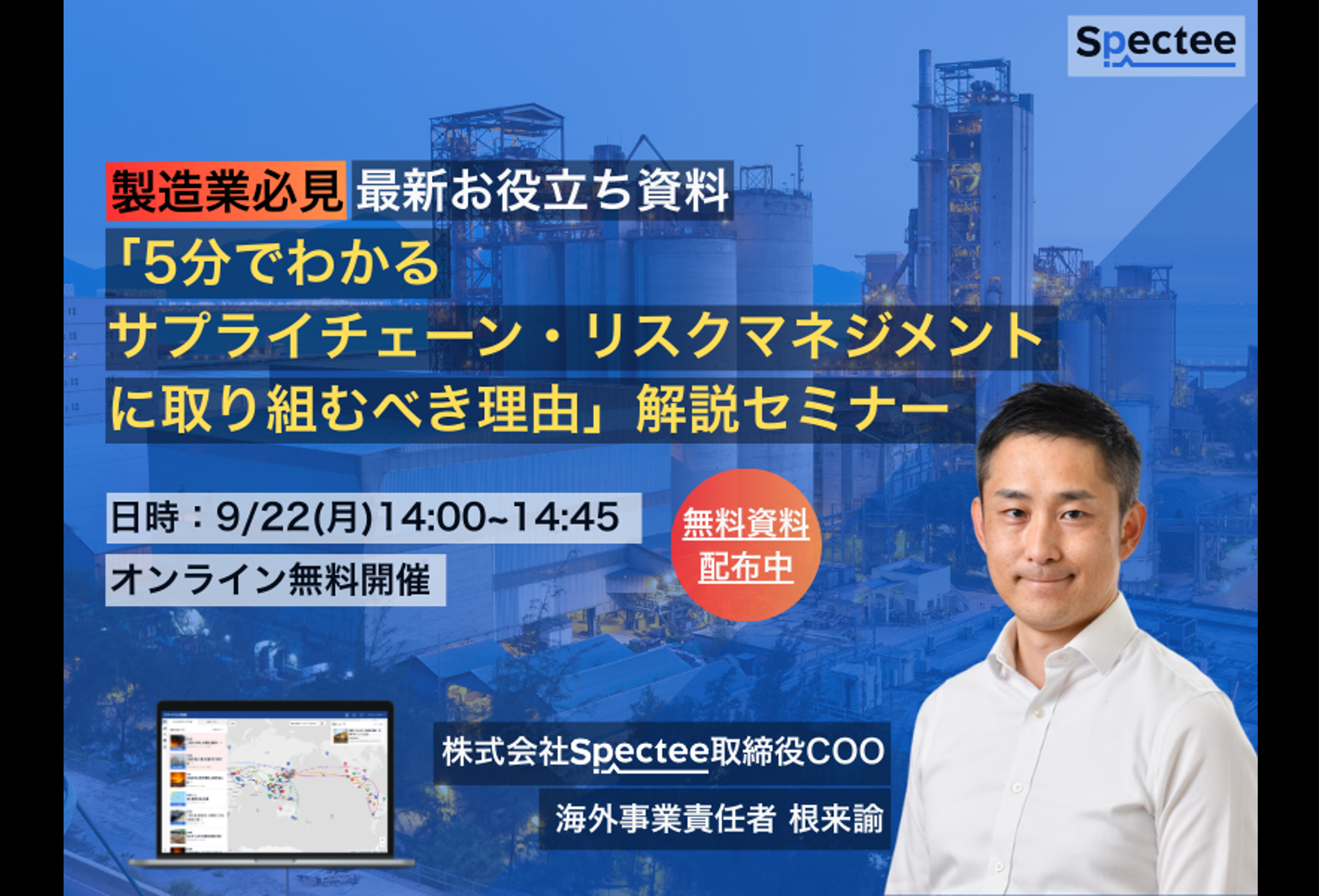製造業を襲うサイバー攻撃:その対応策は?
- テクノロジー
- BCP・危機管理
- ビッグデータ
- レジリエンス
- サプライチェーン
現代の製造業は、IT(情報技術)とOT(運用技術)の融合によるスマートファクトリー化、そしてグローバルに広がるサプライヤー企業との連携によって、かつてないほどの生産効率・コストダウンを達成しました。しかし、この高度で複雑なシステムは、サイバー攻撃に対する脆弱性という新たな経営リスクに直面しています。近年、製造業を標的としたランサムウェア攻撃が頻発し、生産ラインが停止に追い込まれる事例が後を絶ちません。一つの企業の被害が、部品供給の遅延や製品出荷の停止といった形でサプライチェーン全体に波及し、甚大な経済的損失を引き起こすケースも珍しくありません。
事例から見るサプライチェーン寸断のメカニズム
サイバー攻撃がいかにしてサプライチェーンを寸断するのか。いくつかの具体的な事例からそのメカニズムを紐解きます。ケース1:取引先への攻撃が引き起こした生産停止(トヨタ自動車 / 小島プレス工業)
2022年2月、トヨタ自動車のメインサプライヤーである小島プレス工業がランサムウェア攻撃を受け、サーバーがダウンしました。同社はトヨタの「ジャストインタイム」生産方式を支える重要な部品メーカーであり、電子部品の発注や生産計画を管理するシステムが停止したことで、部品の供給が完全にストップしました。この影響で、トヨタは国内全14工場の稼働を全面的に停止せざるを得なくなりました。この事例の教訓は、自社のセキュリティがいかに強固であっても、サプライチェーン上の脆弱な一点を突かれれば、事業全体が麻痺するという事実です。攻撃者は、セキュリティレベルが比較的低いと目される中小の取引先を踏み台にして、最終的な標的である大企業のサプライチェーンに致命的なダメージを与える手法を多用します。自社だけでなく、自社に繋がる全ての取引先のリスクを把握しない限り、防御は成り立ちません。ケース2:物流の要衝を狙った攻撃(名古屋港)
2023年7月、日本の貿易の要である名古屋港のコンテナターミナルを管理するシステムがランサムウェアに感染しました。これにより、トレーラーによるコンテナの搬出入作業が全面的に停止し、港湾機能は2日以上にわたり完全に麻痺しました。自動車部品をはじめとする多くの貨物が滞留し、周辺の物流に深刻な混乱を引き起こす結果となりました。この事例は、製造拠点だけでなく、製品や部品が通過する「物流の結節点(ノード)」もまた、攻撃者の標的となることを示しています。工場が無事でも、港や倉庫といった物流インフラが機能不全に陥れば、サプライチェーンは寸断されます。自社の供給網がどの港や物流ハブに依存しているのかを正確に把握していなければ、こうしたリスクを予見し、事前対策を講じることはできません。ケース3:海外拠点からの広範な影響(アサヒグループホールディングス)
2021年、アサヒグループホールディングスは、海外子会社がサイバー攻撃を受けたことを公表しました。この攻撃により、欧州事業の生産・物流・販売システムに障害が発生しました。直接的な被害は海外でしたが、グローバルで連携する今日のサプライチェーンにおいては、特定地域の生産計画の遅れが他地域の部品調達計画に影響を及ぼすなど、その影響は決して限定的ではありません。地政学的な緊張や各国の法規制の違いから、海外拠点は国内とは異なるリスクに晒されており、グローバルな供給網全体を俯瞰したリスク管理の必要性が浮き彫りになりました。
本質的対策①:サプライチェーンの可視化
上の事例が示すように、サイバー攻撃のリスクは自社の管理下だけには留まりません。したがって、本質的な対策の第一歩は、自社がどのような供給網の上に成り立っているのかを正確に把握する「サプライチェーンの可視化」です。これは、直接取引のある一次サプライヤー(Tier 1)のリストを眺めるだけでは不十分です。その先にいる二次サプライヤー(Tier 2)、三次サプライヤー(Tier 3)、さらには原材料の供給元まで、可能な限り深く掘り下げてマッピングすることが求められます。なぜなら、供給途絶のリスクは、自社から遠く、目の届きにくいサプライチェーンの上流で発生することが多いからです。
可視化を実践する上で重要なのは、以下の二つの視点です。ひとつは「商流と物流のマップ化」です。どの企業から何を購入しているかという「商流」だけでなく、部品や製品がどの工場、倉庫、港を経由して、どのような輸送手段で運ばれてくるのかという「物流」の情報を地図上に落とし込み、「サプライチェーンマップ」を作成することが理想です。これにより、特定の地域やインフラへの依存度が一目瞭然となり、災害や地政学リスクとサイバー攻撃リスクを重ね合わせた複合的な分析が可能になります。もうひとつは「品目単位でのリスク評価」です。企業単位での評価に加え、調達している「品目」単位で、代替調達の難易度やリードタイムを評価します。特に、代替が効かない専用部品や、特定のサプライヤーしか製造できないクリティカルな部材を特定し、その供給経路を重点的に把握することが、リスク管理の精度を大きく向上させます。本質的対策②:リスク監視体制の強化
サプライチェーンを可視化できたら、次は起こりうる変化や脅威の「予兆」をリアルタイムで捉え、先手を打つための「リスク監視体制の強化」が必要です。受け身の対応ではなく、能動的に情報を収集し、迅速な意思決定に繋げる仕組みを構築します。
自社や取引先が直接攻撃を受けたという報道を待つのでは遅きに失してしまう可能性が高くなります。そのため、脅威インテリジェンスサービスなどを活用し、「特定の国や業界を狙ったサイバー攻撃キャンペーンの活発化」や「取引先が利用するソフトウェアの脆弱性情報」といった予兆段階の情報を積極的に収集することが必要です。また、理想的にはこれらの情報を一元的に集約・分析し、サプライチェーン全体を俯瞰して意思決定を行う「サプライチェーン・コントロールタワー」のような専門組織・機能を設置することが望まれます。この司令塔が、リスクの予兆を検知した際に、代替生産の準備や在庫の積み増しといった具体的なアクションを迅速に指示することで、被害を未然に防いだり、最小化したりすることが可能になります。サイバー攻撃によるサプライチェーンの寸断は、もはや単なるIT部門の問題ではなく、経営そのものを揺るがす重大なリスクです。ファイアウォールの設置や社員教育といった個別のセキュリティ対策はもちろん重要ですが、それだけでは巧妙化するサプライチェーン攻撃の前には無力です。
真のレジリエンスを構築するためには、自社の事業を成り立たせているサプライチェーンの全体像を正確に「可視化」し、そこに潜む脆弱性を特定すること。そして、その脆弱性を常時「監視」し、脅威の予兆を捉えて即座に対応できる体制を構築すること。この二つが、これからの製造業にとって不可欠な両輪となります。効率一辺倒のサプライチェーンから、リスクへの耐性と復元力を備えた強靭なサプライチェーンへと転換を図ることこそが、不確実性の時代を生き抜くための最重要の経営課題と言えるでしょう。(根来 諭)
October 08, 2025
信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!
スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。
また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。
製造業向けに新たにサービスを開始した『スマートリスク管理』(https://spectee.co.jp/smart_risk_management)は発生から1分でリスクと被害状況の把握が可能ながらコストを抑えてすぐに開始できます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/
- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)