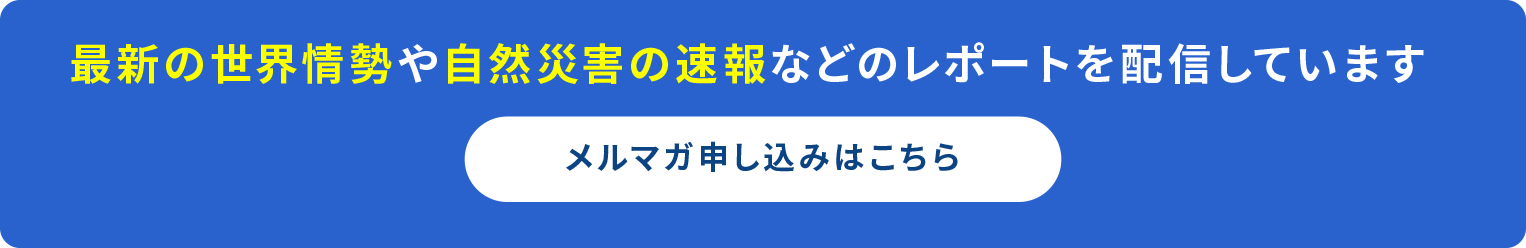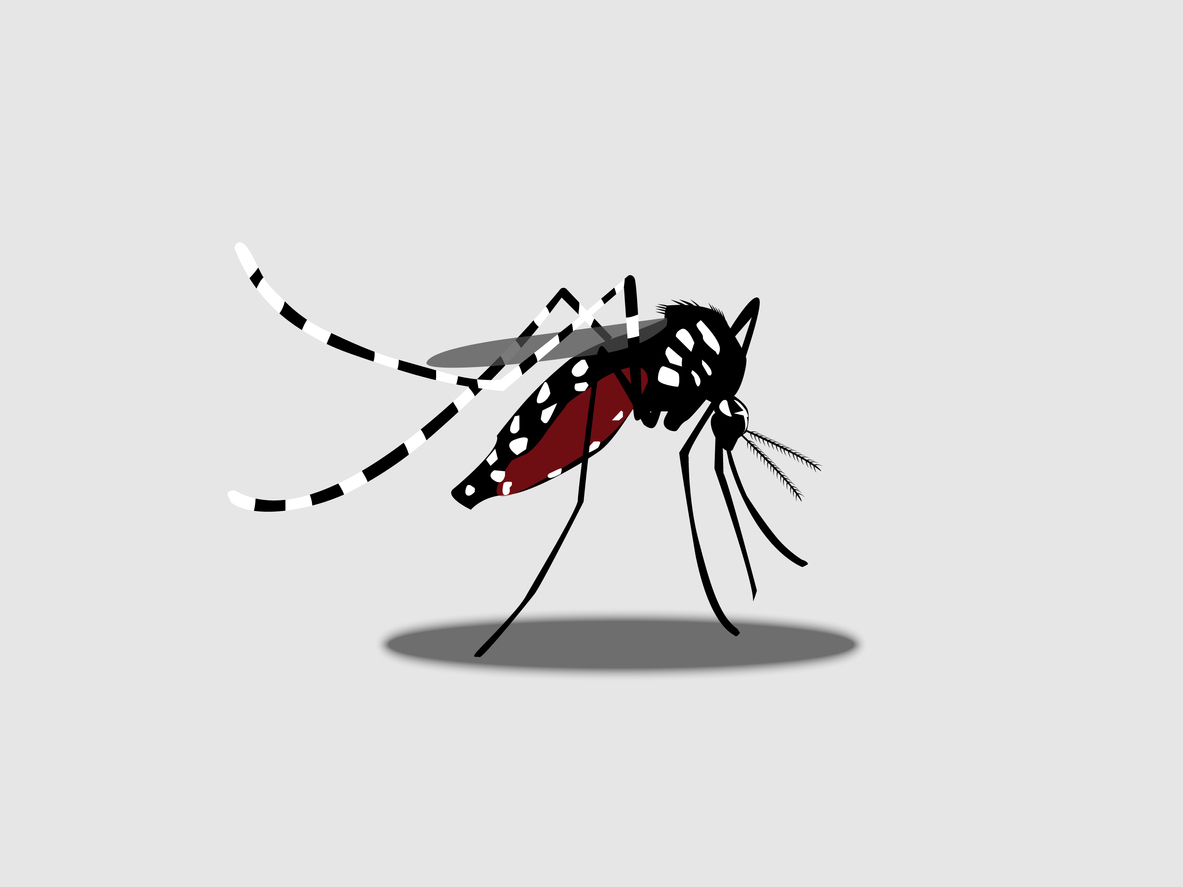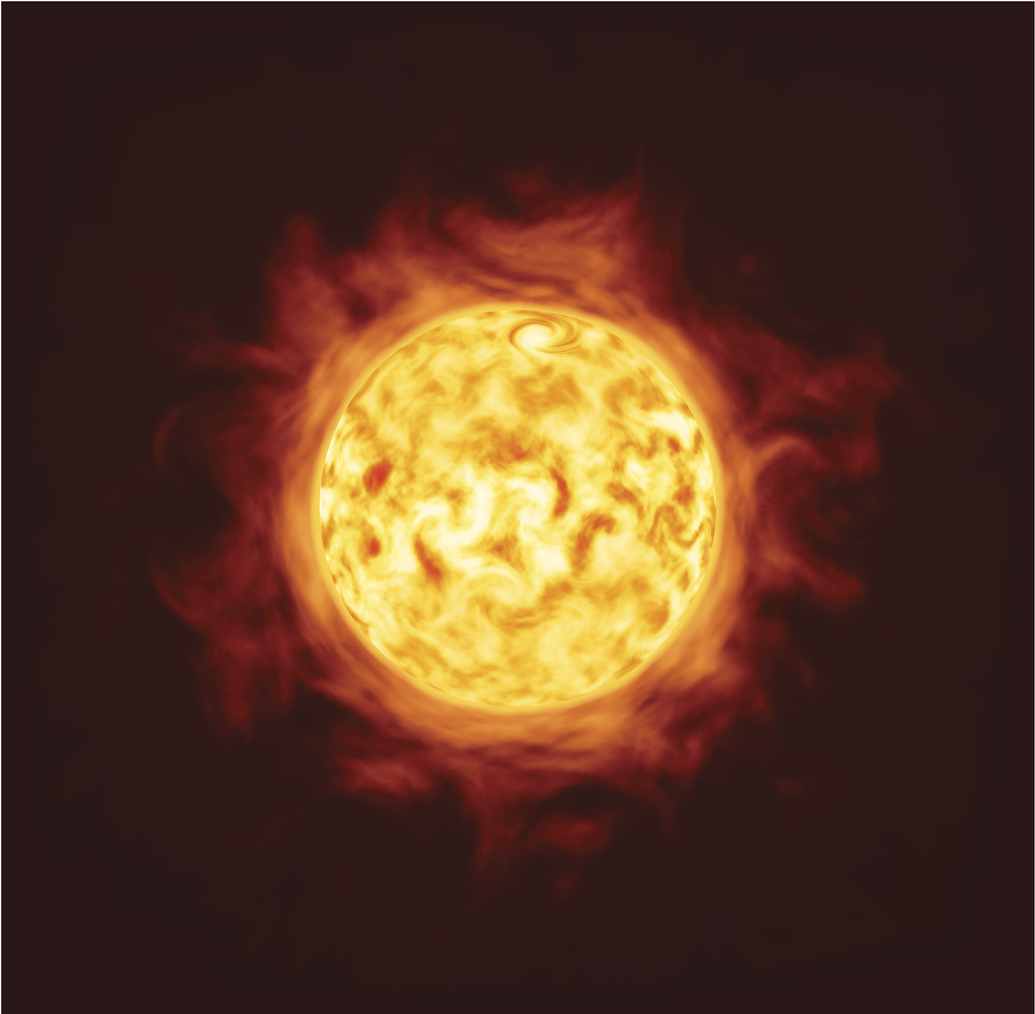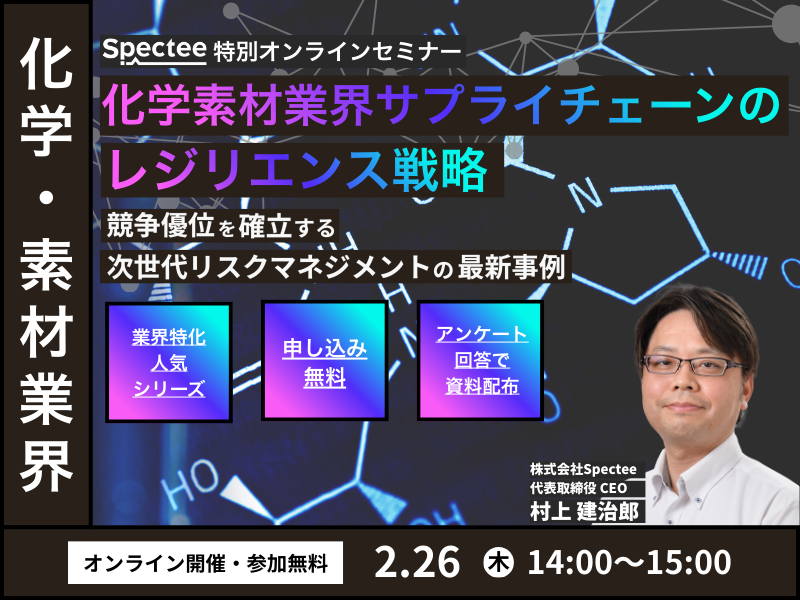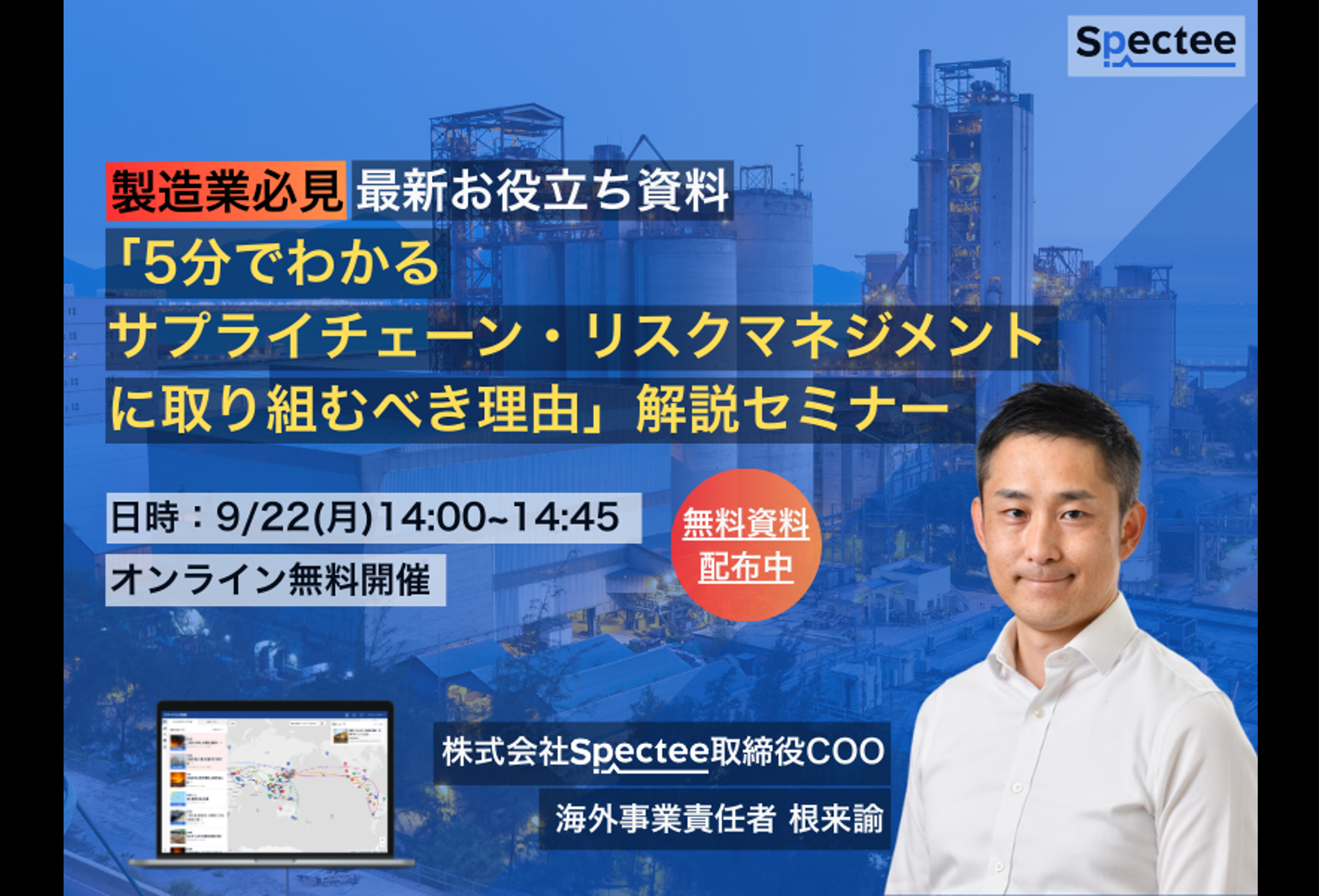ナッジ理論と危機管理:人々を「そっと後押し」してレジリエンスを高める
- 防災
- BCP・危機管理
- レジリエンス
- 自然災害
2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授によって広められたナッジ理論。この理論は、私たちの日常生活から公共政策に至るまで、様々な分野での応用が期待されています。特に予測不可能な事態が頻発する現代において、危機管理分野でナッジ理論がどのように貢献できるか、その可能性が注目されています。本稿では、ナッジ理論の基本的な考え方を解説し、危機管理の様々な局面で、どのようにナッジを活用できるのかを考察します。
ナッジ理論とは
ナッジ(Nudge)とは、直訳すると「(人の脇腹を)肘でそっと突く」という意味です。行動経済学者のリチャード・セイラー教授と法学者のキャス・サンスティーン教授が共著 『実践 行動経済学』の中で提唱した概念で、「選択を禁じることも、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャのあらゆる要素」と定義されています。重要なのは、ナッジは強制ではなく、人々に選択の自由を残したまま、より良い方向へ自発的に行動するよう促す「優しい介入」であるという点です。罰則や金銭的な報酬といった伝統的な行動変容の手法とは異なり、あくまで「そっと後押しする」アプローチを取ります。
ナッジ理論の背景には、人間の意思決定に関する行動経済学の知見があります。伝統的な経済学では、人間を常に合理的で自己の利益を最大化するように行動する「ホモ・エコノミカス(経済人)」として捉えてきました。しかし、現実の人間は、必ずしも合理的に判断・行動するわけではありません。心理学者のダニエル・カーネマン(ノーベル経済学賞受賞者)が示したように、人間の思考には直感的で速い「システム1(速い思考)」と、論理的で遅い「システム2(遅い思考)」があります。私たちは日常生活の多くの場面で、エネルギー消費の少ないシステム1に頼って意思決定を行っており、これが様々な「認知バイアス(思い込みや判断の偏り)」を生み出す原因となります。
代表的な認知バイアスには、以下のようなものがあります。
現状維持バイアス:特に理由がなくても、現在の状況や選択を変えようとしない傾向。
損失回避性:同じ価値のものでも、利益を得る喜びより損失を被る苦痛をより大きく評価する傾向。
同調バイアス:周囲の人々と同じ行動をとることで安心感を得ようとする傾向。
正常性バイアス:自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする傾向。
フレーミング効果:同じ情報でも、提示の仕方(フレーム)によって意思決定が左右される現象。
ナッジは、こうした人間の心理特性や認知バイアスを理解した上で、システム1に働きかけ、より良い選択を促すように設計されます。効果的なナッジを設計するためのシンプルなフレームワークとして、「EAST」が提唱されており、具体的なナッジを考案する際の指針となります。

危機管理分野でのナッジ活用戦略
危機管理の様々な局面で、ナッジはどのように活用できるのでしょうか。EASTフレームワークを参考に、具体的な戦略と実例を見ていきましょう。
戦略1:情報を「分かりやすく、魅力的に」提示し、適切な判断を促す (Easy & Attractive)
危機時には、正確な情報を迅速かつ分かりやすく伝えることが極めて重要です。しかし、情報が複雑だったり、専門用語が多かったりすると、人々の理解を妨げ、適切な行動に繋がりません。

戦略2:「社会的な規範」を活用し、協力行動を引き出す (Social)
人間は、周囲の人々がどのように行動しているかを意識し、それに合わせようとする傾向(社会的規範)があります。これを活用することで、望ましい行動を広げることができます。
戦略3:「デフォルト」や「簡便性」で行動のハードルを下げる (Easy)
人間は、現状維持を好み、面倒な手続きを避けようとする傾向があります。望ましい行動を「デフォルト(初期設定)」にしたり、ハードルを極力下げたりすることで、行動変容を促しやすくなります。
戦略4:「タイミング」を捉え、行動を喚起する (Timely)
情報提供や働きかけは、適切なタイミングで行われることでその効果が大きく変わります。人々が特定の行動について考えやすい時期や、意思決定を行う直前が狙い目です。

さらに危機発生時には、不確実性や不安の高まりによって、デマ情報が拡散しやすくなり、社会に混乱を引き起こすことがあります。こうした状況においてもナッジの手法は有効であり、情報を発信する人と受け取る人の双方に働きかけることで、デマの広がりを抑える助けになります。たとえば、SNSで情報を共有しようとする際に「この情報は信頼できますか?情報源を確認しましたか?」といった注意喚起のメッセージを表示することで、投稿前に一度立ち止まるきっかけを作ることができます。また、政府機関や公的機関、主要メディアなど、信頼性の高い情報源を分かりやすく一覧で示し、誰でも簡単にアクセスできるようにする工夫も効果的です。
まとめ
ナッジ理論は、危機管理の分野において、人々の自発的な協力と適切な行動を引き出し、被害を最小限に抑えるための新たな道筋を示しています。災害時の迅速な避難、感染症の拡大防止、デマ情報への冷静な対応など、その応用範囲は広く、今後さらに多様な場面での活用が期待されます。重要なことは、ナッジを単なるテクニックとして捉えるのではなく、人間の行動特性への深い理解に基づき、倫理的な配慮を伴いながら活用していくという視点です。
危機はいつ、どこで、どのような形で発生するか予測困難です。そのような不確実性の高い社会において、一人ひとりが主体的に考え、行動し、互いに支え合う「レジリエント(強靭)な社会」を構築していく上で、ナッジ理論は強力なツールの一つとなるでしょう。今後、AIやIoTといったテクノロジーとの融合により、さらにパーソナライズされた、効果的なナッジの開発も進むと考えられます。 私たち自身がナッジの対象者であると同時に、身近なところでナッジをデザインする側に回ることもあり得ます。この「そっと後押しする」知恵を理解し、賢く活用していくことが、これからの危機管理、そしてより良い社会づくりに繋がっていくのではないでしょうか。
(根来 諭)
July 16, 2025
信頼できる危機管理情報サービスとして続々導入決定!
スペクティが提供するAI防災危機管理情報サービス『Spectee Pro』(https://spectee.co.jp/feature/)は、多くの官公庁・自治体、民間企業、報道機関で活用されており、抜群の速報性・正確性・網羅性で、危機発生時の被害状況などをどこよりも速く、正確に把握することが可能です。
また、『Spectee SCR』(https://spectee.co.jp/service/specteescr/)はサプライチェーンに影響を与える危機を瞬時に可視化し、SNS・気象データ・地政学リスク情報など様々な情報をもとに、インシデント発生による危機をリアルタイムで覚知し、生産への影響や納期の遅れ等を迅速に把握することができます。

- お問い合わせ:https://spectee.co.jp/contact/
- お電話でのお問い合わせ:03-6261-3655(平日9:00~17:30)